Contents
ヒーリング効果のある悪夢感

一方で人物の内面描写には違った速度が採用されている気がしました。皮肉っぽくて辛辣で、安堂さんご自身の考え方が込められているような。
自分の考えとかはないかな。たぶん、人間がなにかを観察するときって無意識に悪意や辛辣さがあって、画質があがるとシワが見えるのと同じように、文章の解像度をあげようとすると悪意が隠せなくなるのかもしれない(笑)あとは主人公の性格もあって、語り手から少し拒絶されているような読み心地になったのかなとは思います。ちょっと言い足りてなさというか。
例えば「私」のいぶきに対しての気持ちも、「好き」「嫌い」というところに関係も定義し足りていない感じというか。もっと微かで、すぐに消えてしまうような一時的な気持ちを優先して描きたいと思ってました。
もっと恋愛的に描くこともできましたよね。
できるし、しなくてもどうせそう読まれちゃうから。BL読みに抵抗したい気持ちはすごくある(笑)。男性と男性の恋愛の形に置き換えて消費しやすくするみたいなのは拒絶したい。だって、尊厳も保たれていない社会で、キュンキュンとかしてほしくないでしょ! みんなが消費しやすい人間ドラマに回収できない人を描きたかったし、それだけでもエモーションは十分に伝わるはずだから。
「この人の気持ちはこうです」っていう答えがあって、そこをグリップにして読ませるみたいな、「キャラクター相関図至上主義」みたいな小説は、確かに読者としても嫌いですね。
フィクションって、キュンキュンして欲しいからキュンキュンしてる人を出す、悲しい気持ちにさせたいから悲しい話を書くみたいに単純なものじゃないから。今作も起こっているのは悲惨なことだけど、全体的に目指していたのは治癒されるような感覚でした。憂鬱な物語に癒されることって絶対あるから。
疲れすぎていてポジティブなものが見れないとか、ホラー映画を見たくなる人ってけっこういますけど、本当に何も受け付けないほど憂鬱なときに読んでもらえるような、ヒーリング効果のある悪夢感を作りたかった。
『迷彩色の男』というタイトルは、犯人の男がその場その場で色を変えていく、一義的にはその意味だろうと思うんですが、他にも含意がありそうですね。
そこでいう「色」っていうのは属性を象徴するための記号ですよね。私たちは肌の色といった物理的な色についても、さらにそれを象徴としての「色」で区分けしたりするし。小説のなかで物理的な色と、象徴としての「色」をどう処理するかを考えながら、犯人を追って書き進める中で“迷彩色の男”が現れたんだと思います。
マジョリティ側から見てマイノリティとひとくくりに言うけれど、ひとりひとりは個別の人間ですから、いろんな面があって当たり前ですもんね。
この小説みたいに極端でなくても、日常的にもね。たとえばシスのゲイ男性であれば、クローゼットでいる時間は社会的に異性愛者でいれるわけだから、そういうふうに透明性と特権性が一体化してる感覚っていうのもわかるし。迷彩色の男は、起こった現象と属性への偏見を切り離せない、社会側の単一的な見方をむしろ利用している犯罪者像に、最終的には固まっていきましたね。
言葉で見える極限まで書きたい

日本人の男性といえば《単一のイエロー》という言葉も面白くて、自分たちマジョリティが照らし返されている感覚がありました。
マイノリティ側から人種を定義するっていうのはほとんど無意識に決めていました。あとは赤と青以外の色をなるべく出さないって決めていたから、「黄色人種」みたいに色としてすっと入ってくる言葉じゃなくて、それを概念としていること自体に違和感を持ちなおせるような言葉になっていきましたね。
「黒人」って日本語で言うけど、黄色人種のことを「黄人」とは言わないですよね。あとは「ハーフ」っていう言葉はいけないよねっていうコンセンサスが生まれているけど、ハーフの人が何かの半分ではないように、ミックスの人にだけ何かが混じっているわけではないですよね。ほんとに絶対的な正解ってないから、言う側も気を使うと思うんだけど……でも、いま使われているルールもすごく偏ったところに基準があるから。この小説では「私」という人物のための言葉にアレンジしてますね。
色鉛筆の「肌色」問題ですね。
そうそう。だから肌色という言葉を使うにも《いぶきの肌色》にした箇所がありますね。単語自体がダメなわけじゃないから。小説を頭から終わりまで読んでもらって、どんな話だったっていうのももちろん大事なんだけど、そういう細部も大事でしたね。
『ジャクソンひとり』は三人称の小説で、『迷彩色の男』は一人称ですよね。これも島本さんとの対談で話していたことですが、一人称は実体験だと思われてしまうから難しいと。今回はそこをクリアできたから「私」を選んだんでしょうか。
最初の文藝賞応募作が一人称だったんですが、「エッセイに近い文章」という選評をいただいたことがあって、現実的な問題として、公募ってその人の作家としての能力を疑う場でもあるから、私にとっては人称がまあまあなハードルだったのかな。それで『ジャクソンひとり』は三人称で、複数人の人物を書いたり混ぜたりしているうちに、私自身も読み手もどうでもよくなったんだと思う(笑)。最初の小説として他人にどう伝えるかっていうことを限界まで考えて、当時できることは全部企んだ小説でした。『迷彩色の男』は2作目だから出せたものだと思います。読者の方に出会えたのも大きいですね。
《怒りは屈折する》というキーワードがありますが……。
それもやっぱ立つんだよね(笑)。
これは立つでしょう、どうしたって(笑)。
これは作品自体の要約というより、この状況でいぶきはなんて返すんだろう?って出てきた言葉なんですけどね。
シーンの一部としてある言葉なんですね。
そう。いぶきのツイッターを念視したときに、そう書かれてあったみたいな(笑)建物や光と同じ、ビジュアル描写の一個として書いているっていうか。
それと、読みながら僕は『ムーンライト』という映画を連想したんですが、関係はありますか?
書いているときは全く意識してなかったですね。「月光の下でブラックの肌が青くみえる」っていうのは『ムーンライト』以前からある比喩ですし。
そういう定型のロマンティックからさらに踏み込んで、じゃあ「青い電球の下ではどんな人種も青くみえる」っていう状況なら、「ブラック」を「ブラック」たらしめる色以外の要素を前景化させられるとか、ほんともう趣味ですね。概念から自由になって、もう一度ある肉体に出会い直すような場面を作りたくて。
あのあと、いぶきの見た目を取りこぼしのないように形容していく一連の描写がとても素敵でした。
うれしい。ありがとうございます。《ブラックだった》のひとことでもわかっているんだけど、言葉で見える極限まで書きたいという気持ちがありました。ある魅力的な肉体がそこにいて、それを見るというのはどういうことなのか。それを極力具体的に、ガチの目と言葉でやりたかった。
《単一のイエロー》の人たちが他者を見る目線がもっと丹念に、仔細になっていくことに寄与する作品になるんじゃないかと思います。
そうですかね。啓蒙的なモチベーションってあんまりないんですけど、小説を書いているときに、かつて自分が見たものを言葉を通してもう一回見て、すごく輝きが増すことってあるから。それを味わってもらえたらいいなとは思います。
そういえば、単行本の装丁は『ジャクソンひとり』に続いて川名潤さんがやってくださるんですけど、『迷彩色の男』っていうタイトルには、こういう日本語を川名さんのデザインで見たいなっていうのもありました。川名さんも、国籍も時代もわからないようなデザインをなさる方だから。
撮影/中野賢太(@_kentanakano)

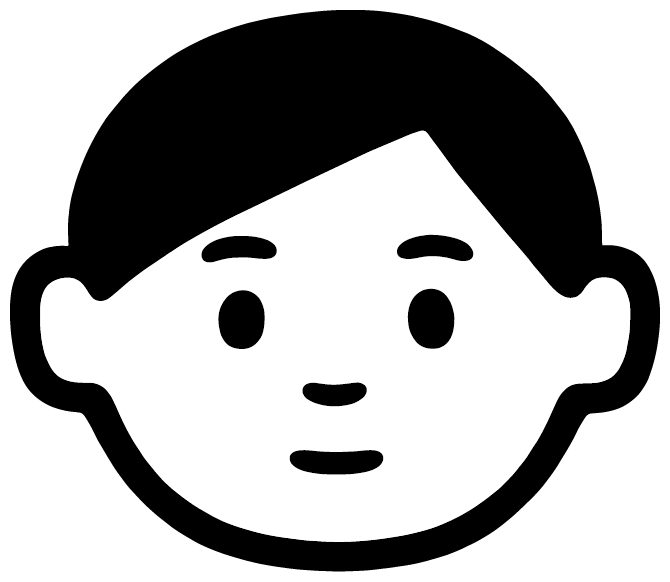 FREENANCE MAG
FREENANCE MAG 


