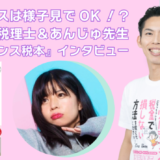読み終えた瞬間、文字通り放心状態になってしまうこと間違いなし。上出遼平さんいわく「自分が出版する最初で最後の“仕事術”の本」という『ありえない仕事術 正しい“正義”の使い方』は、そう断言できるほどの衝撃作です。正義の正体を提起し、人間の弱さ、脆さを描写しながらも、柱になっているのは“あなた”の幸せの在処はどこなのか?ということ。
テレビマンとして出発し、ドキュメンタリー監督としても活躍する上出さんの、社会に対する鋭すぎる眼差しが暴く“不都合な事実”について、現在、居住されているニューヨークとのリモート取材でじっくりうかがいました。
1989年東京都生まれ。テレビディレクター、プロデューサー、作家。2011年テレビ東京入社。ドキュメンタリー番組『ハイパーハードボイルドグルメリポート』シリーズ(Netflixにて配信)の企画、演出から撮影、編集まで制作の全工程を手掛け、同番組はギャラクシー賞を受賞。音声のみで制作した同番組Podcastシリーズ(Spotifyで配信)はJAPAN PODCAST AWARDS大賞を受賞。2022年6月テレビ東京退社後、ニューヨークに拠点を移す。著書に『ハイパーハードボイルドグルメリポート』『歩山録』など。 https://twitter.com/HYPERHARDBOILED
https://www.instagram.com/kamide_/
何が自分の幸せかを知る

一読させていただいて、本当に『ありえない仕事術』というタイトル通りの作品だなと感嘆しました。
はい。ありがとうございます。
最初に衝撃を受けたのが、帯にもある“世に出ている「仕事術」なんて嘘ばっかりじゃないか。”というキャッチコピーそのもので。世間一般の仕事術がゴールとして見定めている“成功”の先に、果たして幸せがあるのか?という疑問は、どんなところから生まれてきたんでしょう?
そこは、今まで作ってきた番組の中で伝えようとしていたこととも共通していて、なぜ世の中にある“幸せ”の形は、こんなに数が少ないんだろう?ということを、ずっと僕は考えてきたんです。なぜ、そういった考えに行き着いたかというと、きっと人よりはいろんな世界の、いろんな人と出会ってきたからだと思います。
その多くが日本と比べれば貧しかったり、危ない地域だったりするんですけど、その日の食事も十分に食べられない家族が、それでもキャッキャッと笑って転げ回っているような瞬間って、東京で暮らしているとなかなか目に入らないじゃないですか。もちろん経済的な豊かさが正しくないという話では全くないですけど、やっぱり日本にいると同調圧力もあって、自分の物差しを持たずに人の物差しを拝借することが身についてしまう。それこそが多くの人の不幸の原因なんじゃないかなと思うんです。
そういった物差しを共有しようとする力の1つがテレビであり、書店に行けば平積みされている仕事術とか自己啓発の本も、実はその役割を担っているように感じるんです。そこで提示されている“幸せ”の形に議論の余地はなくて、結局、そこに至る道のりだけが、いろんなバリエーションで示されているに過ぎない。でも、その先にある形が本当に万人にとって“幸せ”なのか?ということについては誰も語ろうとしないという、そこに不気味さみたいなものを感じていたんです。
本来、幸せの形は人それぞれのはずであって、競争社会で勝つことだけが幸せとは限らない。なので自分自身の幸せの形を見つけるために、自分の心がどんなときに喜びを感じるのか、自分の心を観察する“欲望の整理”を行うことを本書では薦められていますが、では、上出さん自身は、どんな欲望の整理を通じて、何が自分の幸せであると結論づけていますか?
幸せを感じることって当然いくつかあって、なるべくその分量を人生の中で増やしていくようにはしています。例えば、僕は旅からの帰り道に幸福感を覚えることがあります。旅の準備も旅先での時間も楽しいけれど、やっぱり最高なのは帰り道だなという感覚は確かなので、最高の帰り道をたくさん得るために、とにかくたくさん、それもなるべく過酷な旅をしています。パッケージングされたツアーとかではなく、自分の頭と体を使って、ある程度の負荷がかかる旅じゃないとダメなんです。あとは、旅のお土産話をしたときに喜んでもらえたり、話を聞いた人が同じ場所に旅立ったとかっていう経験も楽しいので、どうやって旅を共有するか?ということにも頭を使っています。それがお金になるようにするにはどうしたらいいだろうか?と考えて、 日々を生きてますね。
逆に「これは自分の幸せに繋がらない」と断言できるものも増えてきていて、例えば人気のブランド物を身に着けたり、それを他人に指摘されたりで嬉しかったことは一度もない。そうやって自分の幸せと無関係なものに一つひとつ気づいていければ、それを追いかけたりお金を費やす必要もなくなって、余計なことをしなくて済むんです。「これがきっと自分の幸せだな」と言えるものをいくつか溜めて、それを目がけて物事を考えていけばいいだけだから、今はすごく楽な生き方ができてますね。
本当の喜びは安心感の中にはない

ニューヨークに居を移されたのも、そういった思案の賜物と考えれば納得です。ちなみに、やはり旅は海外のほうが良いんでしょうか?
そういうわけではないですけど、僕は“欲望の整理”において、一貫して安心感を求めていないんです。その点、日本にいるよりもニューヨークにいるほうが限りなく安心感が少なくなりますから、より日々が楽しくなるっていうのはあります。
これは僕個人の感覚なんですが、本当の喜びというものは安心感の中にはないんですよ。漢字では“楽しい”と“楽”って同じ文字だけれど、意味合い的には全くの別物で、安心感から脱しないと得られないものが絶対にあるんです。だけど、やっぱり人間って“安心”だとか“楽”というものに抗えないから、みんなと同じ流行りのものを身に着けて、褒められて……というほうに吸い寄せられてしまう。それって喜びではなくて、きっと安心のほうなんですよね。自分自身が本当に幸せを感じるわけでもないのに、みんなと同じであることの安心感を“幸せ”だと勘違いしている。
もちろん、安心すべきでないとは全く思ってないですよ。好きでもないブランド物を身に着けることが幸せなんだと錯覚したまま死ねるなら、それはそれでいい。でも、もしかしたら死ぬ間際に「どうせ死ぬのに、なんで自分は安心感ばかり求めていたんだろう? 自分の喜びのために危険を冒すべきだったんじゃないのか?」って後悔するかもしれないですよね。それについては本書の第二部でも書いてますが、死というものを意識するかしないかで、人生の選択は全く違うものになるんじゃないかと思ったりもしてます。
安心の正反対にあるジェットコースターみたいな乗り物に、みんな喜び勇んで乗りたがるのも、そういうことなのかもしれないですね。みんな本当は危険を冒すことを求めている。
いや、そこは違うんです。ジェットコースターは安心を大前提としてますから、結局は他人に与えられる喜びというか。僕、ジェットコースターがこの世で一番嫌いなんですね。まず、あのスピードが1ミリも怖くないので、この拘束を受けている5分間はいったい何なんだろう?って、逆に放心状態になってしまうんです。しかも、その途中で「これは100パーセント安全ではない」ってことに気付いてしまうわけですよ。実際、ときどき事故のニュースが出るじゃないですか。じゃあ、なんで自分では全くコントロールできない危険に身を委ねて、しかも、嘘の恐怖を前提とした喜びみたいなものを与えられてるんだろう?と疑問を覚えてしまうんです。僕、映画の『マトリックス』が好きで、何でもコレで例えちゃうんですが……それこそ栄養カプセルの中で架空の楽しい世界を見せられていて、脳みそに刺さってるプラグを誰かにパン!と抜かれたら一瞬で死んでしまうような状態。架空の喜び、架空の安心安全の中にいるだけで、実は全く安全じゃないんです。
そんなジェットコースターと真逆なのが、僕にとっては山に入ることで、危険だらけの世界だけれど、自分の脳と肉体を使って危険を回避して生き抜くことができるじゃないですか。その先に得られる喜びの方が何万倍も手触りがあって、その喜びのうちに死ねたら「生きていてよかった」と思える気がするんです。
停滞や腐敗を回避するには?

やはり一番重要なのは、自分でコントロールできるか否か、なんですね。見せかけの安全を他人に委ねるジェットコースターではなく、自分の知恵と肉体で生き抜くことのできる山を選べと。結局、それが本書でも書かれている「会社に依存せず、自分の足で立てるようになろう」という主張に繋がっているんだなと納得しました。
確かに同じことを言ってますね。気づきませんでした(笑)。要は、会社に属しているという状況がジェットコースターに近いんですよ。何も考えなくても生かしてもらえて、すごく安心できる状況のように見えるけれど、その会社が自分の生きている間ずっと安泰だなんて保証はないですよね。安全だと言われているジェットコースターが稀に事故るのと同じで、自分のいる会社が突然破綻することも十分あり得る話なんですから。そうなったときに、自分の足じゃ立てないくらい会社に依存してたらどうするんだ?っていう話です。その不安や危険性を無視できない世界になってきているから、会社を辞めたがっている人が多かったりするんでしょうね。
だから、少しでも辞めたい人は辞めればいいし、フリーランスになることに臆する必要もない。
可能であるなら、会社に属さない働き方を一度は経験するに越したことはないですよね。もちろん終身雇用が大好きだという人なら、ずっと会社にいるのもいいでしょうけど、1、2年フリーランスでやって、また会社に属するとかでも全然いい。 1つの会社に居続けても、停滞と腐敗からは逃れられない。
特に市場がグローバル化した今の時代、 世界でどう戦っていくか?ということを考えなければいけないわけで、いろんなところを渡り歩いた人間の強さというのは、会社員であっても絶対に必要になってくる。逆に1つの会社に居続けると、その人の競争力は絶対に頭打ちになるから、そんな人間ばかりの組織が海外との競争に勝てるはずがないですよね。そのリスクを回避するためにも、できるだけたくさんの人がフリーランスを経ていくべきだと思います。会社に依存しなければ生きていけない人たちで構成された組織と、フリーランス経験で独り立ちできる力を養った人たちで構成された組織、どっちが強いかなんて想像するまでもないので。
本書には「飲みに行くのなら仕事の仲間以外と」とも書かれてましたが、それも同じ理由ですね。自分とは違う場所で、違うものを見ている人間の視点を取り入れることは、停滞や腐敗の回避には有効ですから。
そうですね。世界が狭いというのは、あらゆる局面で本当に良くない。小さなコミュニティの中だけで生き続けていると、目にできる“幸せの形”が少ないままになってしまうので、それはかなり危険なことですよね。個人の幸せのためにも、物作りをする人間にとっても。幸せの形はコレだと決めつけている人間が作るものって、やっぱり恐ろしいじゃないですか。
そうやって特定の幸せの形を大衆に押しつけ、洗脳することで利益を得ている誰かがいるのかもしれないですしね。
それも『マトリックス』の状況で、結局、全部繋がっているんですよ。与えられる幸せの形を疑いもなく信じるのは、カプセルの中でプラグに繋がれて楽しい夢を見ていることと同じ。自分で思考することを放棄して、他人に答えとかりそめの安心安全を与えてもらう。そんなぬるま湯に浸かっていたら、死ぬときに後悔するかもしれないよという警鐘を鳴らしたいってことです。
結局、みんな不安で苦しい。だから、かりそめの安心を幸せだと錯覚して、それを選択せざるをえない。そういう意味では、その苦しみを味わう必要がない生き方をしてこれた僕は幸運だったと思います。


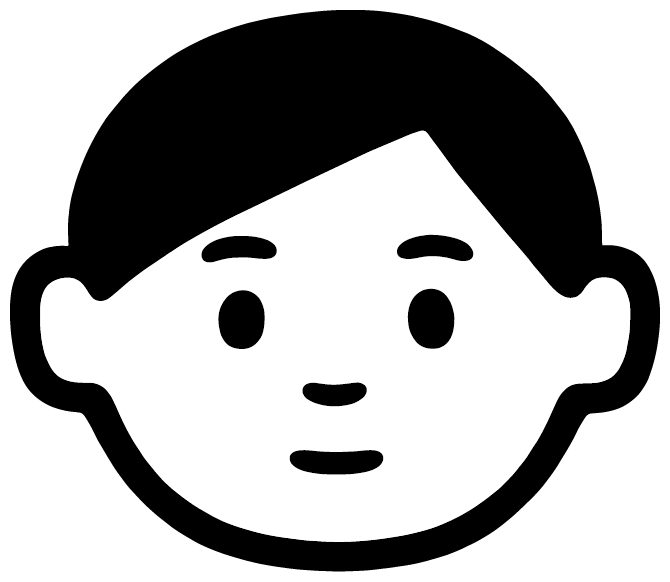 FREENANCE MAG
FREENANCE MAG