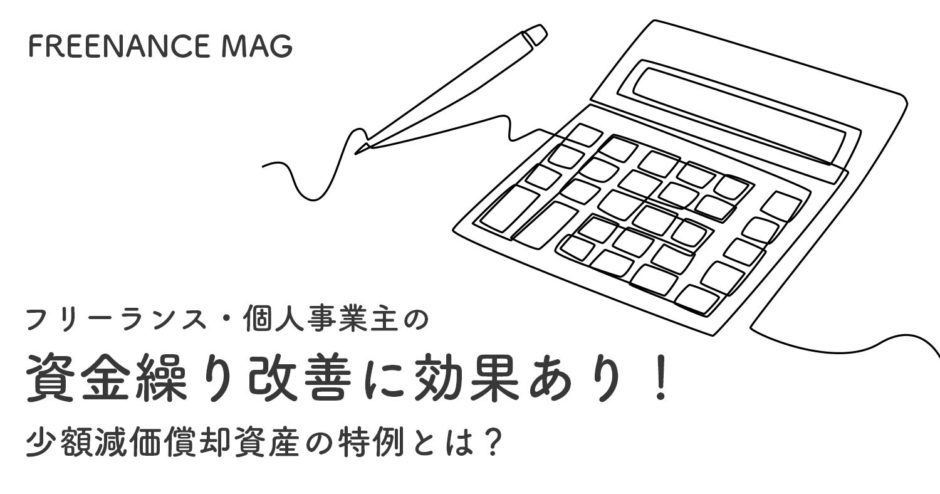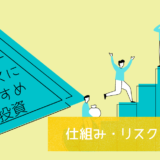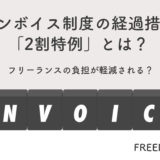事業に必要となるオフィス用品などの事業用資産を購入した場合、通常は固定資産として計上します。しかし、中小企業やフリーランス・個人事業主の場合、「少額減価償却資産の特例」を受けることができます。これは、決められた範囲内であれば、減価償却資産の購入にかかった費用の全額を損金に算入し、当年度の経費にできるというものです。その概要やメリット、特例を受けるための要件などについて解説していきます。

お金と保険のサービスです。
Contents
少額減価償却資産の特例とは?
「少額減価償却資産の特例」は、正式名称を「中小企業者等の少額減価償却資産の取得原価の損金算入の特例」といいます。本特例により、特定の条件を満たした中小企業者は、事業の用に供した「取得原価30万円未満の減価償却資産の一定金額」を損金算入できます。なお、本特例は2年ごとに適用期限が延長されており、令和4年度の税制改正でも2年間の延長が決定されています(令和6年3月31日まで適用可能とされています)。
実は、事業用資産は固定資産として計上しても、取得原価分だけ損金に算入できる点は変わりません。しかし、少額減価償却資産として、早いタイミングで損金に算入することにより、その期の課税所得が小さくなり、税金額も少額になるのです。つまり、結果的に税金の支払いを遅らせることができ、手元に資金が残りやすいというメリットがあります。
※参照:国税庁 No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
減価償却資産とは?
そもそも「減価償却資産」とは、事業用資産のうち、時の経過に応じて価値が減少していく資産のことをいいます。例えば、事務所用の建物、オフィス用品の備品、機械装置が該当します。一方、土地や美術品など、時の経過により価値が減額しないような資産は、減価償却資産とはなりません。
減価償却資産は、税法上、購入時には全額を損金(税務上の費用)に計上せず、耐用年数(資産を利用できる期間)にわたって少しずつ損金算入することが求められています。
減価償却の計算について、具体的な事例を見てみましょう。
⇒価値の減少に応じて1年目~5年目にかけて毎年5万円が損金として計上されます。
取得原価とは?
取得価額が30万円未満の場合には、本特例を適用できます。では、「取得原価」とはどのように計算するのでしょうか。
まず、「取得価額」とは、資産の取得にかかった費用の金額のことをいいます。購入代金だけではなく、不動産の取得費用のような付随費用も加味して計算されます。また、消費税の免税事業者で「税込経理」をしている場合であれば、消費税込みの金額で計算されます。これらの金額が30万円未満の場合には、少額減価償却資産の特例の適用対象となります。
※参照:国税庁 No.5400 減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用
メリットは資金繰りの改善!
少額減価償却資産の特例を利用する最大のメリットは、資金繰りの改善にあります。先にお伝えした通り、なるべく早いタイミングで損金に算入すると、結果的に税金の支払いを遅らせることができるため(課税所得が小さくなることにより税金が小さくなるため)、手元に資金が残りやすいというメリットがあります。
⇒1年目~5年目にかけて毎年5万円が損金として計上されます。
一方、少額減価償却資産の特例を適用した場合は以下の通りです。
⇒1年目に25万円が一括で損金として計上されます。
上記いずれの場合であっても、最終的に、取得原価25万円分が損金処理される点は同様です。ただし、後者(少額減価償却資産の特例)の場合には1年目に全額損金算入されることで、直近事業年度の税金支払いを減らせます(損金が大きくなることにより、直近事業年度の課税所得が減るため)。
他方、翌年度以降の節税効果は見込まれなくなりますが、資金繰り改善の観点では、税金の支払いはできるだけ遅くするのが基本です。その意味では、本特例を利用するメリットは大きいといえるでしょう。
また、会計処理を単年度で完結させることができる点もメリットです。減価償却資産として会計処理を行う場合には、会計システム、スプレッドシートなどを利用し、翌年度以降の減価償却計算を行う必要があります。取得原価、耐用年数といった設定を行うだけでなく、毎年処理漏れがないように償却費を確認するといった手間も発生します。
この点、少額減価償却資産の特例を適用して、一時の損金として処理できれば、事務作業を軽減できます。
対象は「10万円以上30万円未満」と「青色申告者」
ここからは、少額減価資産の特例の適用対象と適用要件について見ていきましょう。
適用対象: 10万円以上30万円未満の減価償却資産
まず、特例の適用対象ですが、取得原価が30万円未満の減価償却資産に限られます。ただし、10万円未満の減価償却資産については、特例を使用しなくとも「少額減価償却資産」として一括で損金算入が可能です。特例の適用対象としては「10万円以上30万円未満」の減価償却資産と理解しておきましょう。
また、適用の対象となる資産の合計金額は年間300万円が上限です。例えば、21万円の資産を15組購入した場合、15組の合計は315万円となり、特例の適用対象は14組まで(294万円まで)となります。
さらに、対象となる資産は取得した年度に実際に使用を開始したものに限られます。年度末に駆け込みで取得しても、実際に使用を開始していない場合、本特例は適用できないため注意しましょう。
適用要件:青色申告をしていること(フリーランス・個人事業主)
次に、適用要件ですが、中小企業者であることが求められています。具体的には、資本金の額または出資金の額が1億円以下でなければなりません(多くのフリーランス・個人事業主は中小企業者であると想定されます)。また、青色申告をしていることや、従業員数が500人以下であることが求められています。
※参照:『少額の設備投資を行った場合の税制措置を知りたい』 少額減価償却資産の特例
よくある疑問
Q.事業年度が1年に満たない場合はどう計算する?
事業年度が1年に満たない場合には、上限金額の300万円を12で割って事業年度の月数を掛けた金額が限度額となります。例えば、最初の事業業年度が3カ月の場合には、「300万円 × 3 ÷ 12 = 75万円」が限度額です。
Q.免税事業者のように税込処理を行っている場合はどう計算する?
税込金額で判定します。例えば、税込で32万円の減価償却資産は、特例の対象外となります。税抜経理の場合に適用可能な資産が、税込経理の影響で適用対象外となる可能性があるので注意しましょう。
Q.特例処理を適用した場合、固定資産税は課税されない?
特例処理を適用した場合であっても、固定資産税の課税対象となります。そのため、固定資産台帳などで物件の管理を行うことが必要となります。一方、10万円未満の少額減却資産の場合には、固定資産税は課税されません。
特例を活用するためのテクニック3つ
300万円枠を分散して利用する
少額減価償却資産の特例には、対象となる資産の合計額が年間300万円までという上限金額があります。この「毎年300万円の」限度額を分散して利用することは、特例のメリットを享受するためのテクニックです。
例えば、X1年度に、特例の対象となる資産(取得原価30万円未満)を、合計500万円分購入しようと検討しているとします。X1年度に500万円分すべてを購入すると、300万円の限度額を超えた200万円分は特例を適用できません。
一方、X1年度に300万円分を購入し、残りの200万円分は、翌年(X2年度)に購入して、取得のタイミングを分散させると、いずれの年度も限度額を有効活用できます。
ただし、これはあくまで資金繰りの観点からの話です。事業計画上、X1年度に資産が必要となる場合には、事業運営の観点と資金繰りの観点を比較しながら決定する必要があります。
耐用年数が長い資産への適用を優先する
また、耐用年数が長い資産を優先して特例の対象とすることも考えられるでしょう。
例えば、耐用年数5年、取得原価20万円の資産と、耐用年数10年、取得原価20万円の資産が、それぞれ合計10組(合計400万円)ずつあったとします。年間の限度額は、合計300万円であるため、すべての資産には特例を適用できず、優先順位をつける必要があります。
資金繰りの観点からは、できるだけ早い時期に損金算入することが望ましいため、耐用年数が長い資産を優先すると良いでしょう。この例では、特例を適用しない場合、耐用年数が10年の資産は、償却の完了が10年後ですが、耐用年数が5年の資産は、5年後に完了します。本件の場合は10年の資産を優先して特例の対象とすることで、資金繰りの改善面で、よりメリットを享受できます。
年度末付近に取得した資産へ適用を優先する
さらに細かい話になりますが、年度末付近に取得した資産へ優先して特例を適用する場合もあります。
例えば、12月末が会計年度末の会社において、1月と10月に取得した取得原価20万円の資産が、それぞれ合計10組(合計400万円)あったとします。
ただし、年間の限度額は合計300万円ですから、優先順位をつける必要があります。この例の場合、通常の減価償却処理だと、1月に取得した資産は初年度に12カ月分の償却費を計上できますが、10月に取得した資産は月割計算上、3カ月分しか計上できません。
繰り返しですが、資金繰りの観点からはできるだけ早いタイミングでの損金算入が望まれます。そのため、期末付近に取得した資産を優先して特例を適用し、全額を年度内に損金処理すると、資金繰り改善のメリットをより享受できます。
適用の手続き
少額減価償却資産の特例を適用するためには、取得原価に関する明細書を添付して申告をする必要があります。ただし、青色申告決算を行っている個人の場合には、「減価償却の計算」欄にこの制度を適用していることなどを記載することにより、明細書の添付に代えることができます。
具体的には、対象資産の行を1行作り、以下のように記載する方法が考えられます。
- 取得原価欄に合計金額、償却の基礎になる金額に明細を別途保管している旨
- 摘要欄に「租税特別措置法28条の2(租法28条の2)」と記載する
※参照:「中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の 特例制度」を適用する場合の明細書の添付について
※参照:記載例
ケースによって適用するか選べる!
資金繰りの観点からは、できるだけ早いタイミングでの損金算入が望ましいため、少額減価償却資産の特例は、積極的に適用すべきと考えられます
ただし、少額減価償却資産の特例は強制適用ではなく、あくまで選択適用ですので、最後に補足をさせていただきます。例えば、今期は赤字で節税効果が見込まれないケースや、事業運営の観点から少しでも今期の利益を大きくしたい場合は、特例を利用しない選択も考えられます。こういった場合は、会社の状況に合わせて選択するようにしましょう。
適用すべき制度を金額別に整理!
10万円未満の資産の場合、特例を利用しなくても「少額償却資産」として一時の損金とできるため、あえて特例を選択する必要はありません。
10万円以上20万円未満の資産の場合、一括償却資産とするか、少額減価償却資産の特例を利用するかを選択できます。一括償却資産とは、3年間にわたり定額で減価償却する方法のことで、資金繰りの観点では、通常の減価償却よりもメリットがあります。ただし、少額減価償却資産の特例を適用するほうがより有利ですので、こちらを優先して利用すると良いでしょう。
20万円以上30万円未満の資産の場合、少額減価償却資産の特例を積極的に利用すると良いでしょう(中小事業者であるなどの要件を満たす必要があります)。一時の費用として計上できるため、資金繰りの観点からは望ましいです。
特例はあくまで選択適用のため、いずれの金額の場合でも、原則どおりに資産計上し、減価償却する方法も認められています。資金繰りの観点からはあまり推奨できませんが、当期の利益水準(税金が発生するかがポイント)を判断軸として選択すると良いでしょう。
まとめ
「少額減価償却資産の特例」は、中小事業者などの一定条件を満たした場合に適用できる減価償却の特例です。耐用年数にわたって少しずつ損金算入するのではなく、初年度に一括で損金算入できるため、資金繰りの観点からは大きなメリットとなります。また、事務処理の観点からもメリットがありますので、要件を満たす事業者は積極的に利用すると良いでしょう。
ピンチにも、チャンスにも。ファクタリングサービス
「FREENANCE即日払い」
https://freenance.net/sokujitsu
▼あわせて読みたい!▼
FREENANCE byGMO
\LINE公式アカウント開設/
LINE限定のお得情報などを配信!
ぜひ、お友だち追加をお願いします。
✅ご登録はこちらから
https://lin.ee/GWMNULLG

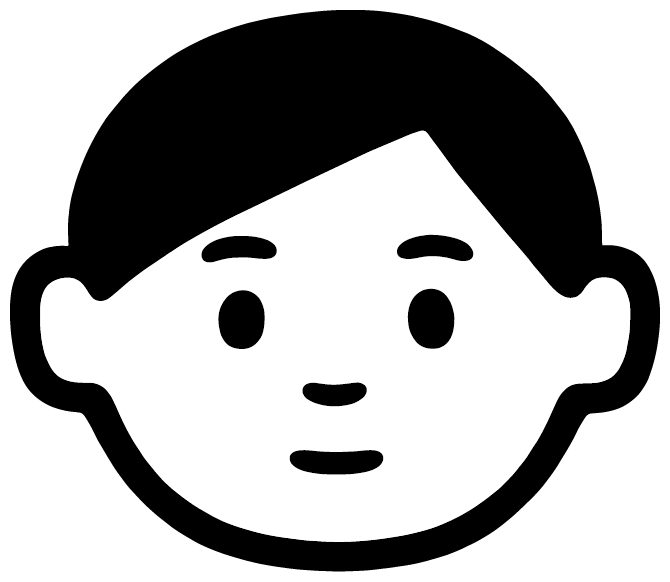 FREENANCE MAG
FREENANCE MAG