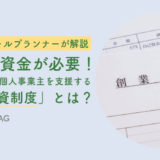本や雑誌を作る上で絶対に欠かせない過程である「校正」。原稿の内容や印刷物の仕上がりをチェックする工程です。その作業を専門に行うプロフェッショナルが「校正者」。一部の出版社は社内に校正/校閲部を擁していますが、大半はフリーランスです。
大西寿男さんは、1988年から数多(あまた)の出版物に関わってきたベテラン校正者。今年5月、2009年に著した『校正のこころ 積極的受け身のすすめ』(創元社)が増補改訂され、関連トークイベントも盛況だそう。誰もが簡単に情報発信できるいま、注目を集める「校正のこころ」とは?
1988年より、主に文芸書・一般書の校正にたずさわりつつ、編集・DTP・手製本など自由な本づくりに取り組む。本づくりと校正のひとり出版社「ぼっと舎」を代表。企業・大学やカフェ等で校正セミナーの講師も務める。2016年、“言葉の寺子屋”「かえるの学校」を共同設立。
著書は、『校正のこころ』(創元社)『校正のレッスン』(出版メディアパル)『かえるの校正入門』(かえるの学校)『セルフパブリッシングのための校正術』(日本独立作家同盟)など。
https://twitter.com/bot_sha
http://www.bot-sha.com/
編集者から校正者へ
大学を卒業後、すぐに校正のお仕事を始められたんですか?
いえ、短期間ですが最初は編集でした。もともと本が好きで、高校生ぐらいのときから小説を書いたり、同人誌を作ったりしていたんです。大学では考古学を専攻しましたが、編集者になりたかったので、新卒のときに東京の出版社をたくさん受けました。ところが全部落ちまして(笑)、「どうしようかな」と思っていたときに小さな編集部に拾ってもらったんです。そこで半年あまり編集や校正など一通りを学んで、そのあと小さな本屋さんでアルバイトをしていたときに、友達の編集者から声をかけてもらって『文藝』(河出書房新社)の増刊号の校正をお手伝いしました。
それがプロフィールにある1988年ですね。
出版がアナログからデジタルに切り替わる最後のあたりですね。そのときに当時の『文藝』編集長の高木有(たもつ)さんから「君は編集者よりも校正者に向いているから」と校正者になることを強く勧められたんですが、あくまで僕は編集者になりたかったんです。おそろしいことに、当時は編集者のほうが校正者より偉いと思っていたので(笑)。でも、ほかにとくにあてもなかったので始めてみたら、高木さんのおっしゃる通り、自分に合っていたという。編集の仕事は、企画を立てるのは楽しいんですけど、会議を通して予算を取ってくるのがつらいなぁ、と。それよりも、じっくりと原稿や、原稿をページの形に組んだ校正刷り(ゲラ)と向き合って、徹底的に読み込む実務のほうが性格に合っていたんでしょうね。
始めた当時、印象深かったことなどはありますか?
いまは新型コロナで難しくなりましたが、「出張校正」といって、印刷会社や出版社の校正室に詰めて、編集者も校正者も一緒に、みんなで集中的に校正していくんです。自分以外みなさんベテランで、飲んだくれの人もいれば競馬に強い人もいるし、冗談ばっかり言っている人もいれば議論が好きな人もいる、という感じで、ひとりひとりがすごく個性的でした。だけどいったんゲラに向かうと、すごく厳しいというか真剣で、その凜とした姿にすごく憧れましたね。
もうひとつ印象的だったのは、河出書房特有のものだったかもしれませんが、校正者を編集者がすごく尊重してくれるんですね。上から目線で下請け扱いするようなことがなく、意見もちゃんと聞いてくれるし、接し方も対等でオープンでした。なので仕事はやりやすかったですし、気がついたことも言いやすかったですね。
以降ずっと校正者でいらっしゃるんですよね。
そうです。ただいろいろやりたい人間なので、ひとり出版社(ぼっと舎)を立ち上げて自費出版物の制作を請け負ったり、趣味で私家本や手製本を作ったりもしてきました。編集、組版、デザイン、営業、広告、ひと通りコンスタントにやってきたなぁと思います。
アナログからデジタルへ
本作りそのものがお好きなんですね。
はい。DTP(※)の時代になって、パソコンとソフトとプリンタがあれば、全部自分でできる世の中になりました。アナログの時代の同人誌作りといったら、まず印刷所にお願いしないといけないですし、活版印刷や写真植字はお金がかかるので手書きの原稿を和文タイプライターで打ち直してもらったり、ワープロ専用機が出てきたら自分で打って印刷し、版下に切り貼りしていました。そのころのことを思うと、本当にいい時代になったなと思います。しかもインターネットで情報発信もできちゃうなんて、5000年にわたる本の歴史上、初めてのことですよね。わくわくします。
※DTP:デスクトップパブリッシング。パソコンを使っておこなう、出版物の制作やリリース。
アナログ時代からデジタルへと激変する環境に、ずっとキャッチアップされているのがすごいです。
頑張ってついてきました(笑)。だって、楽しいじゃないですか。それに、デジタルで合理化・機械化できるところはどんどんそうしたいですよね。校正ってやることがいっぱいありますから。例えば用字用語の統一にしても、アナログ時代にはひとつひとつメモを取って五十音順に並べて、その言葉が出てきたページを書き込んで、それをリスト化して……という、ものすごく面倒なことをしていましたけど、いまはPDFがあれば即座にもれなく検索できます。データ入稿になって手書き原稿とゲラの突き合わせ作業がなくなり、いきなり素読み(※)から始められるのもありがたいです。
※素読み:突き合わせ(引き合わせ)校正のあとに、原稿を離れてゲラだけを読んでおこなう校正。
デジタル時代になって楽になった半面、困ったところもあるのでは?
昔はまず編集者が時間をかけて原稿整理をして入稿していましたが、いまはとにかくデータをフォーマットに流し込んで、文章のブラッシュアップはゲラでやればいい、というスタンスが主流に変わりました。なので、最初の校正刷り(初校ゲラ)はかなり粗かったりするんですが、その段階で校正者が関わって、用字用語の統一から誤字脱字、事実関係のチェック、表現や文章の整合性、時系列まで、一度に何から何まで見るというのは大変すぎますし、ムダが多いです。本来は編集者が原稿整理の段階で解決していた作業も含みますから。それで時間が圧倒的にたりなくて、もっと突っ込んだところ、内容や文章表現に関わる部分のチェックに時間を割きたいのに割けないというジレンマがひとつありますね。もうひとつは、校正だけじゃなく、印刷や製本も含めて、職人技みたいなものがどんどん消えていくことです。
確かに……もったいないですよね。
あと、事実関係を確認するために当たる資料がいまはネット中心になりました。それはすごく便利で早い反面、ネット検索で得られる情報の限界や信頼性の問題もあります。あることを調べたいときに、どこの図書館に行ってどんな資料に当たればいいとか、図書館のどの書棚に行けば自分が欲しい情報があるとか、そういう調査能力、レファレンス能力が校正者には求められるんですが、そういう力を鍛える機会が失われてきているのも問題です。時間の余裕がないことはあらゆる局面に影響を与えていますね。編集者にしてもデザイナーにしても校正者にしても、とにかく早く次の工程に回さなきゃいけないから、自分のところにゲラをいつまでもとどめておけないというのもあると思います。


「言葉を味わう」経験をしよう
それはライターも同じです……。腹が立つこともあるでしょう。
短期間かつ安いギャラで完璧な仕事を求めてこられるところでしょうか(笑)。先ほどの原稿整理のように、本来は編集の仕事なのに、時間がないからとこちらに期待されることもあります。ひどい場合は、「文意が通じてなかったら直しといてください」とか「キャプション入れといてください」とか。それは校正の仕事じゃなくなっちゃうので、とお断りしますけど。別にリライトとして依頼されればよいのですが……とお話ししていて思い出しましたが、こういった校正者の報われない思いや恨みつらみをなんとかしたいというのは、第1版を書いたときの裏テーマのひとつでした(笑)。
『校正のこころ』には随所に言葉を擬人化したような記述があって、とても言葉を愛しておられるのだなと思いました。そういう人が制作のプロセスに関わることで、メディアの言葉の質を高めていけるんじゃないかと。
紙であれWebであれ、文字情報の品質を高めていかないといけない、ということは、この本を書いた最初からすごく思ってきました。誤字脱字はもちろん、不適切な表現や事実関係の間違いは可能な限りなくしていかないといけない。それだけでなく、言葉がよりよく伝わるために、読者対象に合った表記や文字組み、表現を考えることも必要です。校正はたんなる“間違い探し”ではありませんから。最初から完璧な原稿はありません。著者が「本当はこう言いたかった!」という言葉を見つけるためのお手伝いが必要です。校正は、メディアだけでなく、みんなが情報発信できるいまの時代に、誰にとってもすごく大切で不可欠なことだと思っています。
100パーセント同感です。
あとは「言葉を味わう」ということがもっと増えてほしいですね。刹那的に情報を受け取って処理するだけではなくて、ひとつの言葉、ひとつの文章、一冊の本をじっくり味わう。その機会が近年どんどん減ってきている気がするんですよ。学生さんや若い方から「校正の仕事に就きたいんですけど、本をたくさん読んだほうがいいでしょうか」と聞かれることがよくあるんですが、「編集者になりたいならそうですが、校正者になりたいならむしろ一冊をじっくり読むほうがいい」とお答えしているんですね。一冊の本とちゃんと付き合うというか、ひとことひとこと、ひと文字ひと文字を自分の中に染み込ませるように味わいながら読む経験が、あとから生きてくるんです。
そのお話はご本の中でもひときわ印象的な《校正者は著者の側にも読者の側にも立たない。ただゲラの言葉の側にのみ立つ》というマニフェストに通じますね。プロフェッショナルとしての校正者の矜持を強く感じたくだりでした。
ありがとうございます。その部分はこの本で示せた、独創的なところのひとつだと自負しています。「校正者の仕事ってなんだろう」ということを突き詰めて考えて、行き着いた僕なりの答えがそれでした。校正者の校正と編集者の校正はどう違うのか、あるいは違わないのかという疑問がずっとあったんですが、それを考えるときひとつのヒントになったのが、校正者は著者と会わない、手紙やメールのやりとりもしないということでした。機会があっても避けるんですよ。どうしてかというと、著者に会ってしまうとどうしても遠慮をして、チェックが鈍ってしまうから。あくまで客観的に必要なことを指摘していくためには、生身の著者を知らないほうがいいんです。それに、小説の校正をしていて、主人公や語り手が著者の顔や声になっちゃったら、困るでしょう?(笑)校正者は何より目の前のゲラに書かれてある言葉を大切にしようとする。それが、《校正者は著者の側にも読者の側にも立たない。ただゲラの言葉の側にのみ立つ》というフレーズになりました。
《言葉の理解のために、みずから進んで受け身となる「積極的受け身」の態度》はライターやインタビュアーにも通じますし、共感する部分が大きかったです。
そう言っていただけてうれしいです。僕はデザイナーもライターも校正者とつながっていると勝手に思っているんですよ。クリエイターというかアーティストというか、そういう無から何かを創造する存在ではないので、わたしたちは。デザイナーはどんなにクリエイティブなデザインワークをしていてもアーティストとは違うし、ライターも小説家や詩人とは違う。クライアントの需要に応じた文章世界を作っていますからね。わたしたちはあくまでも、本という創作物が生まれるのをサポートする援助職なんです。
言葉との「ほどよい」距離感
校正者の社会的地位をもっと上げる方法はないんでしょうか。
ちょっとずつ上がってきているとは思います。広く関心を持ってもらうことが必要だし、理解もしてもらわないといけない。そのためには校正者が書いた本がもっと出て、たくさんの人に読まれてほしいですし、いまはみんなSNSやブログを使って自分の言葉で語り始めているので、これがひとつにまとまっていけば……と思うと希望はめちゃくちゃあります。長らく校正者は便利な日本語自動修正機みたいに扱われてきましたが、仕方のない部分もあったと思うんですよ。これまでずっと黒子に徹して、黙ってきましたから。だけど、ひとりで文句を言っていても何も変わらないから、これからは自分が大切にしている校正の仕事についてもっともっと発信していかないといけないし、時には戦わないといけないなと思います。
これまたライターも同様ですね。最後に、大西さんがお考えになるフリーランスのいいところとつらいところを教えていただけますか?
つらいほうからいきますと、全部自分でやらないといけない上に、替えがいないことですね。体調が悪くても突発的な事故があっても自分で対処しないといけないし、校正の仕事だけじゃなくて経理もマネジメントも営業も交渉ごともしなきゃいけない。社会的保障もない。いいほうは、人に雇われているんじゃなく自分が自分を雇っているという、個人事業主の潔さです。ただ、サラリーマンも自分が自分の雇用主であるという意識があったほうがいいとも思います。終身雇用の時代でもありませんし、自分の身は自分で守らないといけないのは同じですから。そのときに自分の言葉の品質を保証するスキル、ツール、態度としての「校正のこころ」が大事になっていくと思うんです。校正は何も校正者だけのものではない、みんなのもの。それがこの本で一番伝えたかったことです。
なるほど。ますます業界外の方に読んでほしい本ですね。
あと、言葉と付き合うのが少し楽になるかもしれません。校正って、ゲラの言葉の世界にドップリ浸かってもいけないし、突き放しすぎてもいけなくて、ほどよい距離感を保たないとチェックができないんですよ。自分の言葉とも他人の言葉ともいい感じの距離を保とうとする校正の知恵や態度は、いまみたいにいろんな言葉に翻弄される世の中には役に立つかもしれないと思います。
ただ、そうした距離の取り方や「積極的受け身」は、経験がないとちょっと抽象的に感じる人もいるかも……とも思いました。
介護とか教育とかボランティアとか、人間と直接関わる仕事を経験されている人のほうがよくわかってくれるかもしれないですね。この本で「対面しつつ寄り添う」とか「校正は創作者ではなくて援助職である」と言っているのは臨床心理学の影響もありますし、「積極的受け身」の語のベースになったのは「アクティブリスニング」なんです。
「傾聴」ですね。僕がすんなり飲み込めたのは編集経験よりも、昔カウンセリングをかじったことがあるからかもしれません。
校正や出版の話をしながらも、そういう側面が常にどこかあるんだろうなと思います。なので「スピリチュアルの香りがする」とか「自己啓発的な感じがする」と言われることがたまにあります(笑)。校正の話を通して言いたかったのは「言葉とどう付き合うか」ということですし、言葉との付き合い方は「人間とどう付き合うか」ということとほとんどイコールなんですよね。「目の前のこのひと文字をどうするか」ということは「目の前のこの人に対してどうするか」「困っているこの人の問題をどうするか」ということと同じなので、校正の仕事は決して理念や思想ではなく、あくまでも実際的な実務なんです。
さっきおっしゃったゲラの言葉との距離感も、人間との距離感に置き換えられますしね。
はい。第2版で伝えたかったのが、「まず理解することから始める」ということでした。校正者は基本的に担当する本を選べません。小説もあれば実用書もあるし、硬い本から軟らかい本まで、依頼があれば同じように引き受けます。自分の好きな本や得意な本ばかり選んで校正するわけではないんです。だから、校正しようと思えば、まず何が書かれているかを理解しないと、この箇所が誤字脱字なのかもわからないし、句読点やカギカッコの位置が正しいのか、間違っているのかもわからない。まったくの初対面の人に向かって、「そこ、間違っていませんか?」「こう言ったほうがより適切じゃないですか?」とアドバイスするようなものですからね(笑)。そこが面白いところであり、大変なところでもあるんですけど、いまの世の中は「まず理解すること」がすっ飛ばされることが多い気がしていて。相手が何を言おうとしているのか、まずはちゃんと聞いて受け止めないと、何も始まりませんよね。生の言葉の現場だとなかなか難しいですが、近すぎず遠すぎず適度な距離を保ちつつ、相手が何を言っているのか理解すること。その二つは同じことというか、車の両輪みたいな関係かなと思います。

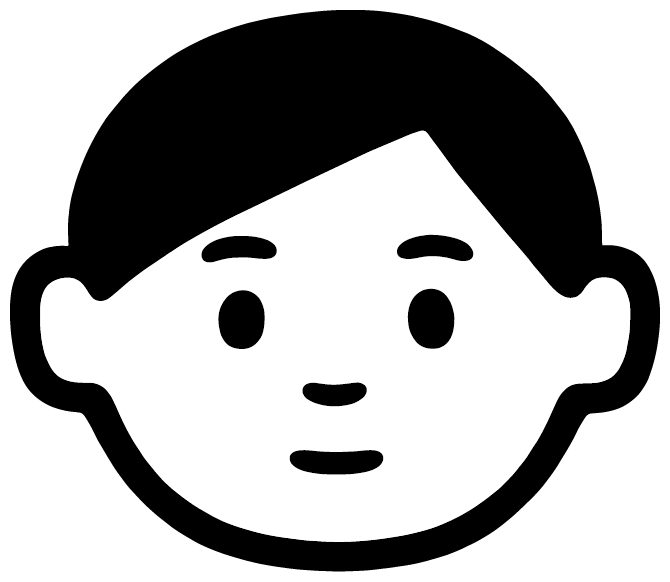 FREENANCE MAG
FREENANCE MAG