閑静な住宅街と商店街が広がる西千葉の街で、毎年【西千葉子ども起業塾】というイベントが開催されています。千葉市と千葉大学が連携し、小学生が起業のノウハウを体験できるという本イベント。仕掛け人でもある、千葉大学教育学部教授・藤川大祐さんにお話をうかがいました。
Contents
子どもたちが会社の経営を「本格的」に体験するプログラム
まずは「西千葉子ども起業塾」がどんなものかを教えてください。
2010年から千葉市と共同で始まったキッズアントレプレナーシップを育むプログラムを「西千葉子ども起業塾」という呼称で実践しています。年に1回、2か月ほどかけて子どもたちに会社の経営を体験してもらうプログラムです。数人ずつに分かれてそれぞれが会社を作り、それぞれの年ごとに定められている「業務」を行うというのが基本的な流れです。

業務というと、どのようなことを行うのですか?
たとえば2019年度の課題は、JFEスチール様からの依頼で「鉄に興味を持ってもらうためのノベルティづくり」というものでした。子どもたちが制作会社や代理店として、ノートやトートバッグなどの企画からデザイン、納品までを一貫して請け負う形でプログラムが進んでいきます。
かなり本格的ですね。
このプログラムの基本的な考え方は、「子どもたちを一人前として扱う」ということです。私は、子どもを子どもとして扱うことで、子どもたちが学び損ねていることが非常に多くあるわけと考えています。仕事に向き合う姿勢として、大人と同等のものを目指してほしいのです。

仕事ですから当然、利益を上げることを目指しますし、子どもたちが行う業務は必ずBtoBということにもこだわっているんですよ。
なぜ、BtoBにこだわるのですか?
BtoCだと、小学生が頑張っている姿を見た消費者が、甘くなることが想定されます。西千葉子ども起業塾は、「大人として仕事をしてほしい」というコンセプトで行なっていますから、BtoBの仕事に限定しているんです。
実際の企業や銀行がクライアントに。本物さながらに業務を遂行
BtoBの仕事を行うとなると、クライアント企業の存在が必要になりますが、西千葉の商店街や千葉市の企業がクライアント役をしてくれています。実際に会社経営を行っている社長が子どもたちにアドバイスをしたり、クライアントが実在の企業や銀行員だったりと、仮想世界ですがすべて本物の人が行っています。

- 塾長:千葉大学の学生が担当。プログラムに沿って、業務が滞りなく完了するための責任を負う。
- 会社付き:千葉大学の学生が担当。基本的には子どもたちの安全確保と業務の成立をサポート。
- 取引先:子どもたちの会社に業務を委託する企業。現在はJFEスチールが取引先。
- 社会人アドバイザー:実際の経営者が担当。子どもたちの会社の社長に経営の課題などをアドバイスする役割を担う。
- 何でも屋:千葉大学の学生や社会人が担当。西千葉市という架空世界と現実の千葉市を結ぶ人。デザイナーをアサインしたり、必要なものを購入したりしてくれる。
- 西千葉銀行:千葉銀行の行員が担当。会社経営では融資が必要になるため、千葉銀行の行員が西千葉銀行の行員として業務を行ってくれる。
- 西千葉税務署:千葉東税務署の職員が担当。消費税や所得税、法人税などの知識を教えてくれる。
なぜ、このようなプログラムを立ち上げたのですか?
簡単に言うと、千葉市から千葉大学に協力依頼があったからです。千葉市では、アントレプレナーシップ(起業家精神)を子どものころから育むことが必要だと考えていたというのが背景ですね。私自身が、新しい授業の実践開発などの教育プログラムの開発に携わっていたこともあり、共同研究という形で始まりました。

「大企業に就職すると安心」という時代はすでに終焉を迎えつつある
子どものうちから起業について学ぶことで、どんなメリットがあると考えていますか?
「大企業に就職すると安心」という価値観は日本特有のものだと感じています。その価値観が社会全体を覆っているため、起業する人が諸外国に比べて少ないという状況にもつながっています。そして現代の教育システムは、産業の時代に均一な能力を持った人を大量に生産するために作られたシステムになっています。
しかし、そういった時代はすでに終焉を迎えつつあります。社会が変化する中で、新しいビジネスを生み出す想像力と創造力、つまり起業家精神が大事になっていきます。雇われる力を身につけるのではなく、生み出す力を養う場が「西千葉子ども起業塾」という位置づけです。

自分なりの特技や人脈を使って人と違う仕組みを作る。それが生きづらさを感じないコツ
なぜこれからの社会では、起業家精神が重要になってくるのでしょうか?
日本という社会において、働くということの形が変わりつつあります。20世紀は、将来のために努力して楽しみは後にとっておく。いわば我慢のゲームが主流でした。しかし終身雇用制が崩壊し、大企業も安泰ではないことが知れ渡った21世紀では、今という時間をどう生きるかが大切になっていきます。
ストレスをかけずに、自分のペースで仕事をする。自分なりの特技、人脈、スキルを使って、人と違う仕組みを作り上げていく。そういう働き方ができるようになると生きづらさを感じないし、食いっぱぐれもないのではないかと考えています。
「西千葉子ども起業塾」の可能性についてどのように感じていますか?
アントレプレナーシップ自体、日本ではあまり浸透していないですから、拡がりもこれからなのではないかと考えています。千葉市と一緒に、今以上に多くの企業や団体が関われるような仕組みにしたいですね。
そして、子どもたちにとって、テレビゲームより会社の経営のほうが面白い、といった価値観が生まれていったら、日本はもっと楽しい国になるのではないかと期待しています。
千葉市との協議では、今後、拡大方向に進もうということになっているので、そのための仕組みを考えているところです。私の個人的な考えとしては、それぞれの地域の独自の素材を使う形で、オリジナリティのある起業家教育プログラムができていくことを期待しています。そして、こういったプログラムが千葉市を起点にして、全国に拡がることを願っています。
取材・文/FREENANCE MAG編集部
ピンチにも、チャンスにも。ファクタリングサービス
「FREENANCE即日払い」
https://freenance.net/sokujitsu
▼あわせて読みたい!▼

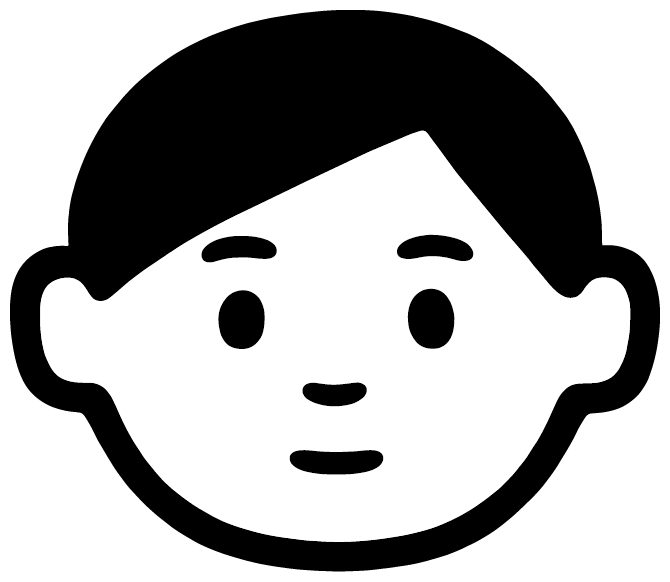 FREENANCE MAG
FREENANCE MAG 



