どうも。
これを執筆している只今、我が社は絶賛決算期でございマス。
昨年から法人化し、代表取締役社長になったはなったんですが、現在ワタクシ劇団ひとりならぬ社員ひとりでございますゆえ、やっていることは個人事業主時代とそう変わらないのでございマス。
確定申告あるあるだと思うんですけど、作業していると、領収書の管理方法とか、メモの保存とか、「あ~こうしておけばよかった!!!」ってことが山のように生まれ、「来年は絶対やっとこう!」っていう来年への傾向と対策ができるのに、次の年にはまるまる記憶がなくなっているという……
あれなんなんですか?
怖すぎやしませんか?
まじで毎年、確定申告に対する全ての記憶を奪われて、「ここはなに?ワタシはどこ?」状態になる自分にビックリしますわ。ええ。そんで呆れますわ。ええ。
……え、ワタシだけですか?
……やだ、うそ、あるあるですよね、あるある……
あるある……
さ、気を取り直して始めましょうか。
Contents
書けるの?書けないの?どっちなんだい!
<前話のあらすじ>
フリーランスとなった天真みちるの元へ「エッセイを書いてみませんか」というオファーがくる。
依頼人である左右社の担当者さんは、なんと「歌劇」という、宝塚歌劇団の月刊機関紙の読者であり、その中の「えと文」という、花・月・雪・星・宙組の各組から一人ずつ選ばれた担当者が3カ月連続で投稿する連載の、当時の私の担当回を読んでいる……いうなればヘビー読者であった……!!
そんなこんなで、担当者さんの宝塚歌劇団への熱意と愛にほだされた私はオファーを快諾(^^)
その後エッセイの大まかなテーマについての打ち合わせをした。
担当者さんと話し合ううち、「私が宝塚歌劇団を受験してから卒業するまで」のエピソードを書くのはどうか、ということになった。
「なんかエピソードあったっけか……?」と、フワッと人生を反芻しながら、
「ちなみに、文字数はどれくらいですか?」とフワッと聞いた。
すると担当者さんは
「最低2500字で、増える分には構いません」と答えた。
天真脳内「……あれは寒い冬の朝の事じゃ……受験資金を貯める為、雪の降り積もる山の頂へ巫女のアルバイト面接へと向かっにせんごひゃく?!?!?!?!」
受験生時代のエピソードがフワッと走馬灯のように流れていた脳内に、突如「にせんごひゃく」というとんでもない数字が飛び込んできた。
以前、朗読劇の脚本を担当することになった際(8話参照)、1時間ほどの作品で22000文字ほど書く必要があった。
それから比べれば約10分の1ではあるが……
自分のエピソードだけで、だぜ?
自分自身のエピソードで2500文字も書けるんだろうか……
思考回路はショート寸前だったが、表側は平静を装い、
「2500文字ですね、はい……」と答えた。
「ちなみに、何話くらい書いたらいいんですか?」と恐る恐るフワッと聞くと、
担当者さんは
「24話くらいを想定しています」と答えた。
にじゅうよんわ……!!!!!!
ワイのタカラヅカライフオンリーストーリーで24話!
そんなに……そんなにエピソードあるもんかいな……!!!!
思考回路はショート寸前だったが、表側は平静を装い、
「24話想定ですね、はい……」と答えた。
「ちなみに、期限とかってありますか……?」と恐る恐るフワッと聞くと、
担当者さんは
「1カ月後とかでいかがでしょうか」と私に問うた。
この時、私の思考回路はショート寸前というかショートした。
ショートした脳内で、
「おい!オレの脳内。おい!オレの脳内。さあ、やるのかい?さあ、やらないのかい?どっちなんだい!?」
と、なかやまきんに君の声がこだまする。
1カ月後に最低2500文字のエッセイを書ききる、という経験などないし、1カ月後の自分を想像してみるしかなかったし、想像もつかんかったし……。
でも、この先もやったことのないことに挑戦するという人生が待っているんだし……
だったら……
天真「はい……やって……みます」
私は、花組公演『カリスタの海に抱かれて』の鳳月杏(ほうづき・あん)演じたクラウディオと違わぬ抑揚と声色で返事をしたのであった。
その道の教科書
その日の帰り道……
やると返事してしまったことで、私の脳内は不安で埋め尽くされていた。
そもそも、この私がエッセイの仕事を請け負うなんて考えもしていなかった。
確かに「歌劇」の「えと文」を書いてはいたし、宝塚歌劇団はお手紙文化も盛んではあった。
けれども在団中、自分の想いは「演じること」でしか伝えられないと思っていたし、「どう演じるか」ということだけを考えて生きていた私にとって、「書いて」伝える技術など無に等しい。
誰かに手取り足取り教えて頂きたい……エッセイのお教室とかあるかしら?
今から行って習って1カ月月後までに習得&入稿できるかしら……?
いや、間に合わんかもしれない……。
あとは何ができるだろうか……。教科書とか売っているかしら……参考書は……。
その瞬間、脳裏に『もものかんづめ』が浮かび上がった。
そう。さくらももこ先生の。
何故この瞬間まで思いつかなかったんだろう。
私にとって、エッセイといえば『もものかんづめ』じゃないか……!
小さいころから幾度となく読み返してきたじゃないか……!
そう気づいた私は走って家に帰り、そのまま本棚から『もものかんづめ』を手に取った。
今までただ純粋に「まるちゃんの記憶力スゲー!」などと思いながら読んでいたのだが、「書くこと」を意識してみると、「何が起きているのか」が目の前に見えてくるような文章、登場人物一人一人が愛おしくなってくる描写の細かさなど……とにかくすべてが素晴らしすぎた。あまりの素晴らしさに本自体が発光しているような感覚に陥った。
……レベチ過ぎる。
自分ごときが「参考書」扱いしようとするなどおこがましいにも程がある。
身の程をわきまえろよ案件だった。
私はそっと本を閉じ、瞳も閉じた。
「……とりあえず書いてみるか」
こうして私は裸一貫で臨むこととなった。

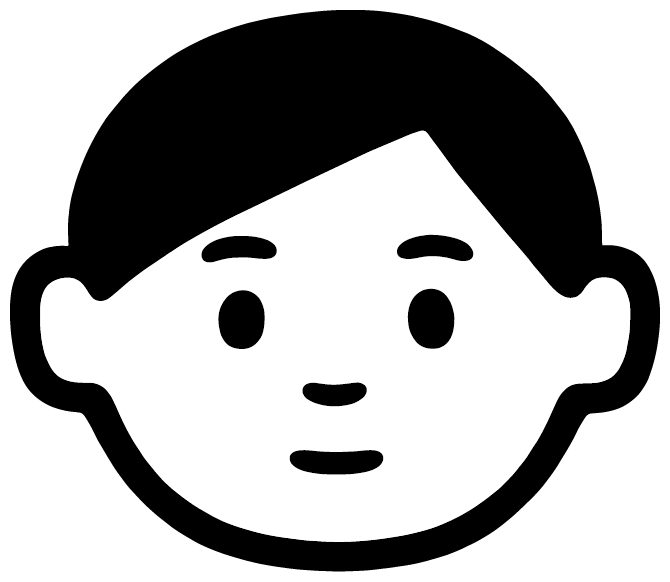 FREENANCE MAG
FREENANCE MAG 



