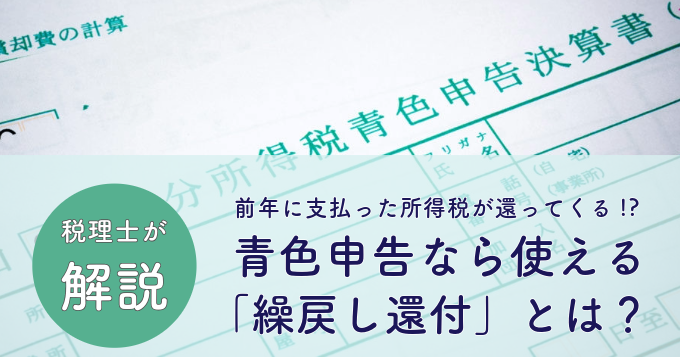個人事業主やフリーランスが確定申告で青色申告をすると、所得税の「繰戻し還付(繰戻還付)」を利用することができます。これにより、例えば新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けて大きな赤字に転じてしまった場合など、前年に支払った所得税の還付を受けることができます。資金繰りに活用できる制度ですのでぜひ覚えておきましょう。

お金と保険のサービスです。
Contents
繰戻し還付制度とは?
「繰戻し還付」は、過去に申告した年度に発生した黒字と、当年度に発生した赤字を相殺することができる制度です。この制度により、過去に申告した際支払った所得税額と、今年の赤字との相殺後の利益で計算した所得税額との差額について還付を受けることができます。還付により実際にお金が入ってくるので、赤字による資金不足を早期に解消できる点がメリットです。
※参照:国税庁[手続名]純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求手続
繰戻し還付の計算例
例えば、令和2年度において課税所得金額400万円であった場合、所得税額は37万2,500円(復興特別所得税除く)となります。そして、令和3年度において、事業損失△300万円となったとしましょう。この場合、どれくらい還付されるのでしょう?

令和2年度分の課税所得400万円と、令和3年度の事業損失△300万円を相殺すると課税所得100万円となります。課税所得が100万円の場合の所得税は5万円です。従って、令和2年度において、実際に支払った37万2,500円との差額である32万2,500円を「繰戻し還付」の利用により還付を受けることができます。

繰戻し還付の利用の仕方
個人事業主やフリーランスに課される所得税や住民税、事業税などは、事業から得られた利益(所得)にかかってきます。その金額は暦年1年間(1月から12月まで)に獲得した利益をベースに計算されます。
つまり、その年が黒字であれば納める税金が発生し、赤字であれば利益に対する税金はかかりません。
事業を継続していれば、ある年で大きな赤字となってしまうこともあります。そのような場合には、資金繰りの面において厳しくなることが考えられるでしょう。
赤字の年には税金がかからなかったとしても、資金が乏しくなっているにもかかわらず、翌年に黒字回復したときにはそのまま、その年の利益に対し税金がかかってきます。
黒字回復したとはいえ、前年の赤字で失った資金を取り戻そうにも、今年に多くの税金を支払わなければならないとなると、資金面で乏しいままで、場合によっては事業の存続すら危うくなる可能性も考えられます。
そこで、「繰戻し還付」を利用し、当年度の赤字を申告すると、過去の申告で支払った所得税の還付を受けることができ、資金が乏しくなることを解消することができます。
制度を利用できるのは青色申告者のみ
「繰戻し還付」を利用できるのは、原則として青色申告事業者であり、前年において青色申告で確定申告をしている人が対象です。例えば、令和3年度において「繰戻し還付」を利用したいのであれば、令和2年度において青色申告で確定申告をしていなければなりません。
従って、令和2年度が白色申告で、令和3年度が青色申告の場合は、残念ながら令和3年度の「繰戻し還付」を受けることはできません。
なお、コロナ禍で事業の廃業を余儀なくされた人もいるかもしれませんが、廃業した年までは青色申告は有効です。従って、令和2年度も青色申告を行っているという条件を満たしていれば、令和3年度で事業を廃業しても「繰戻し還付」が可能です。
※参照:国税庁 No.2070 青色申告制度
※参照:はじめてみませんか? 青色申告
繰戻し還付を利用する際の注意点
「繰戻し還付」は、国税(所得税)にのみ適用されている制度であるため、住民税や事業税などの地方税には適用されません。
また、「繰戻し還付」の請求があった場合には、税務署側でその内容を調査し、還付を決定することになります。従って、税務署からの問い合わせや、税務調査の可能性があることにも注意が必要です。
申請手続
「繰戻し還付」を行うためには、損失(赤字)が発生した年度分の確定申告期限までに手続きをする必要があります。コロナ禍において生じた令和3年度分の損失を申告して「繰戻し還付」を行う場合は、2022年(令和4年)3月15日までに青色申告により確定申告をしなければなりません。
医療費控除や住宅ローン控除などには過年度5年間は所得税の還付を請求することができますが、「繰戻し還付」には5年間の還付請求は認められていない点に注意してください。
また、「繰戻し還付」を申請するためには確定申告書に加え、「純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求書」の提出が必要です。この申請書は国税庁Webサイトよりダウンロードすることが可能です。必要事項を記載し、確定申告書と同時に提出してください。
※参照:国税庁 [手続名]純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求手続
「繰越控除」との違い
「繰戻し還付」と同様に、過去の損益と相殺できる青色申告のメリットとして、純損失の「繰越控除」という制度があります。
ここまで解説したとおり「繰戻し還付」は、過去の黒字と今年の赤字を相殺することができる制度です。一方、「繰越控除」は今年の赤字を翌年度以降に繰り越して、将来の黒字と相殺できる制度です。そのため、将来、黒字になるまではその効果を得ることができません。
「繰戻し還付」と「繰越控除」の判断基準
赤字となった年度において「繰戻し還付」と「繰越控除」のいずれを採用するかについては判断を要します。では、どちらを採用すべきか、その判断基準について見ていきます。
とにかく早急に資金不足を解消したいと考える場合は、「繰戻し還付」を採用するべきでしょう。「繰戻し還付」は上でも述べたように、現金として実際に還付(口座に入金)されるので、ダイレクトに資金不足の解消につながります。
一方、「繰越控除」を採用すれば、還付ということはありませんが、翌年以降3年間に得た利益と相殺することができます。従って、赤字ではあるものの、それほど資金不足ではない場合に、その赤字を翌年以降3年間で相殺できる程度に利益を確保できる見込みがあれば「繰越控除」を採用した方がいいでしょう。
また、「繰越控除」を採用する場合、その影響は大きく、所得税や住民税、事業税、さらには国民健康保険料にまで節税が可能です。一方、「繰戻し還付」を採用すれば、所得税のみが還付され、住民税や事業税、国民健康保険料は影響を受けないことにも留意してください。
そして、「繰戻し還付」を申告すると、一般的に税務調査の可能性があることに留意が必要です。ただし、「繰越控除」を採用すれば、税務調査の可能性はないということではありません。
今年に発生した損失を全額「繰戻し還付」請求せず、一部を 「繰戻し還付」 請求し、残額については「繰越控除」を採用し、翌年以降3年間繰り越して翌年以後の所得金額から差し引くということも可能です。
まとめ
ご紹介した「繰戻し還付」は、申告期限までに確定申告の手続きが必要であることに注意してください。また、青色申告の場合は「繰戻し還付」と「繰越控除」のいずれも選択することが可能です。「繰戻し還付」を利用して早期に資金を確保するか、「繰越控除」で将来の税負担を減らすか、どちらが適切かの判断をしましょう。判断に迷う部分があれば、税理士などの専門家に相談することもおすすめします。
日本初のフリーランス向けファクタリングサービス
「FREENANCE即日払い」
会員登録自体は通常1時間以内で完了。会員登録を申し込んだその日に即日払いを利用することも可能です。
https://freenance.net/sokujitsu
▼あわせて読みたい!▼

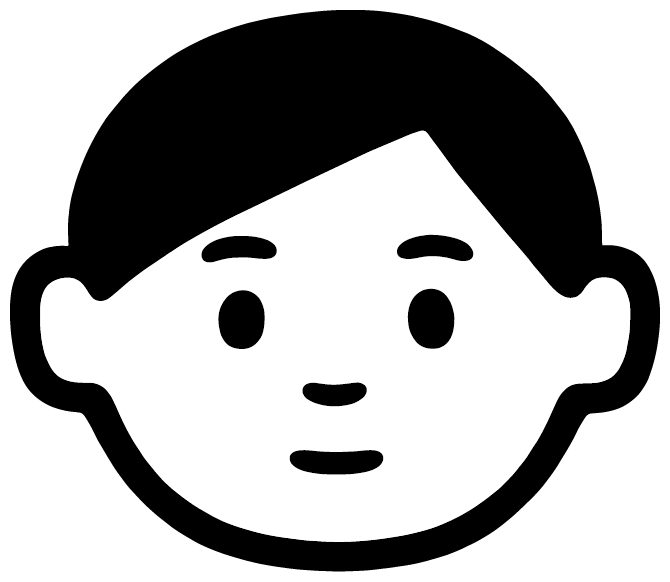 FREENANCE MAG
FREENANCE MAG