2021年(令和3年)4月1日より中小企業にも適用された「パートタイム・有期雇用労働法」。今回は、同法律が施行された目的であり、「働き方改革」の大きな柱でもある「同一労働同一賃金」について解説していきます。
同一労働同一賃金は、フリーランスや個人事業主にとっても、関わりのない話ではありません。将来的な事業拡大に備えて人材を雇うことを検討していたり、「法人成り(法人化)」を見据えていたりする場合は、節税対策や社会保険への加入などと同じく、知っておきたい知識のひとつといえるでしょう。
パートタイム・有期雇用労働法が目指す「同一労働同一賃金」
通称「パートタイム・有期雇用労働法」は、正式名称を「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」といいます。従来の「パートタイム労働法」が改正され、有期雇用労働者が法の適用対象に含まれました。
大企業に対しては2020年(令和2年)4月1日より施行されており、中小企業に対しては1年間の猶予期間を与え、2021年4月1日より施行されています。
この法律は、同一企業内で同じ仕事をする正社員(無期雇用フルタイム労働者)と非正規社員(短時間労働者・有期雇用労働者・派遣労働者)との間の不合理な待遇の差をなくすことを目指す「同一労働同一賃金」を主な目的として制定されました。
同一労働同一賃金は、「労働者がどのような雇用形態を選択しても待遇に納得して働き続けられる」ようにするための改正であり、働き方改革の大きな柱のひとつといえます。
※参照:厚生労働省「パートタイム労働者、有期雇用労働者の雇用管理の改善のために」
※参照:厚生労働省「同一労働同一賃金特集ページ」
対象は「パートタイム労働者」と「有期雇用労働者」
パートタイム・有期雇用労働法の対象となる労働者は、「パートタイム労働者」と「有期雇用労働者」です。
パートタイム労働者とは?
パートタイム労働者とは、1週間の所定労働時間が、同一の事業所に雇用される通常の労働者における1週間の所定労働時間にくらべて短い労働者をいいます。「短時間労働者」と呼ばれることもあり、正社員などの正規労働者よりも労働時間が短い人が、パートタイム労働者にあたります。
会社では、「パートタイマー」「アルバイト」「臨時社員」「準社員」などと呼ばれる人がパートタイム労働者にあたることが多いのですが、呼び方にかかわらず上記の定義にあてはまれば、パートタイム労働者として取り扱われることになります。
有期雇用労働者とは?
有期雇用労働者とは、事業主と半年や1年など期間を定めた労働契約を締結している労働者をいいます。ポイントは、契約期間の定めがあるという点です。会社では「契約社員」や「嘱託社員」などと呼ばれる人が、有期雇用労働者にあたることが多いでしょう。
派遣労働者も広義で同一労働同一賃金の対象
派遣労働者は労働者派遣法の適用対象となるため、パートタイム・有期雇用労働法は適用されません。もっとも、労働者派遣法でもパートタイム・有期雇用労働法と同様に、正社員と派遣社員との間の不合理な待遇差が禁止されています。したがって、結論としては派遣労働者も同一労働同一賃金の対象になります。
改正のポイントは3つ!
パートタイム・有期雇用労働法のポイントには、以下の3点が挙げられます。
1. 不合理な待遇差を禁止
同じ企業で働く正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間で、基本給や賞与、手当などあらゆる待遇について「不合理な差」を設けることが禁止されました。
ここでいう不合理な待遇差の具体例は、厚生労働省が公表している「同一労働同一賃金ガイドライン(短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針)」に挙げられています。
同一労働同一賃金をめぐって争いとなりがちな基本給について見てみると、通常の労働者とパートタイム労働者・有期雇用労働者ともに能力・経験・業績・成果・勤続年数等の決定要素が適用されている場合には、その決定要素に関して、通常の労働者(正社員など)とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間で違いがない場合には、同一の基本給とする必要があります。
例えば、正社員もパートタイム労働者・有期雇用労働者も、勤続年数のみによって基本給が決まる年功序列制の場合には、同じ勤続年数である限り正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者の基本給は、同一にしなければなりません。
同一労働同一賃金は、基本給や賞与をめぐって争われるケースが多いですが、福利厚生施設や社宅、慶弔休暇の利用などの福利厚生や教育訓練、安全管理などに関しても不合理な待遇差の解消が求められることに注意が必要です。
2. 待遇に関する説明義務を強化
事業主は、パートタイム労働者・有期雇用労働者から、正社員との待遇差の内容や待遇差が設けられている理由などについて説明を求められた場合、説明しなければなりません。当然ながら、労働者が待遇に関する説明を求めたことを理由として、事業者が労働者に不利益な取り扱いをすることはできません。
それだけでなく事業者は、パートタイム労働者・有期雇用労働者が説明を求められるよう、配慮しなければなりません。例えば、労働者が「説明を求めれば不利益な取り扱いを受ける」と感じるような言動は慎む必要があります。
3. 裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備等
不合理な待遇差等に関する労使間のトラブル解決のため、都道府県労働局では、無料・非公開の紛争解決手続を利用することができるようになりました。
この裁判外紛争解決手続は「行政ADR(エーディーアール/Alternative Dispute Resolution)」と呼ばれるものであり、事業主と労働者との間の紛争について裁判をせずに解決する手続きです。裁判手続きとは異なり、迅速かつ柔軟な解決ができる点にメリットがあります。上で挙げた「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由に関する説明」についても行政ADRの対象となります。
「待遇差」判断のための支援ツールや相談窓口
パートタイム・有期雇用労働法において導入された同一労働同一賃金は、大きなインパクトを与えるものでした。多くの日本企業が、正社員とそれ以外の労働者との間に待遇差を設けていたからです。
もっとも、労務管理や人事評価の手法は企業によってかなりバラつきがあります。このため、自社の制度がパートタイム・有期雇用労働法が禁止する不合理な待遇差にあたるか否かを判断することはそれほど簡単なことではありません。
そこで政府は、企業がパートタイム・有期雇用労働法に適切に対応することができるように、以下のような事業主向けの支援ツールや相談窓口を設けています。
1. パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書
まず、各企業は自社において必要な取り組みを判断する必要があります。このような場面で活用できる支援ツールとしては、厚生労働省による「パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書」があります。
この手順書では、アンケートに答えることで、企業にとって必要な対応が判断できる仕組みになっています。
また、手順書内には待遇差に関する企業の検討内容を書き込む欄が設けられています。企業がパートタイム・有期雇用労働法への対応をきちんと行ったことの証跡を残しておくためにも、検討内容は書面で残しておくことが大切です。
これに加え、手順書の末尾にはパートタイム労働者・有期雇用労働者に対する待遇に関する説明をする際の書式例も用意されています。随時活用するとよいでしょう。
2. 働き方改革推進支援センター
事業主の相談窓口としては「働き方改革推進支援センター」が47都道府県に設置されています。各センターに配置されている社会保険労務士などの専門家が、無料で事業主からの労務管理に関する相談に乗ります。
働き方改革推進支援センターへの相談は、企業規模の大小を問わず、すべての事業主が利用できます。各センター窓口での相談のほか、電話・メールなどで相談することもでき、専門家が企業に直接訪問して相談対応をすることも可能です。
3. 職務分析・職務評価の導入支援
各企業において、正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者の基本給が不合理な待遇差かどうかの判断や、公正な待遇を確保するためのツールとして「職務分析・職務評価」と呼ばれるものがあります。
職務分析とは、職務に関する情報を収集・整理し、職務内容を明確にすることをいい、職務評価とは、社内の職務内容を比較して、その大きさを相対的に測定する手法をいいます。いずれも、企業の人事において用いられる人事評価とはまた異なるものです。
政府は、事業主への支援のひとつとして、職務分析・職務評価の手法により、パートタイム労働者・有期雇用労働者と正社員との間の待遇差に関する状況を把握し、賃金制度の見直しを支援するための外部専門家(職務評価コンサルタント)を無料で派遣しています。
※参照:パート・有期労働ポータルサイト「職務分析・職務評価とは」
まとめ
これまで日本企業では、正社員とそれ以外の労働者の間で待遇差が設けられているケースがよくありました。働き方改革の一貫として導入された同一労働同一賃金は、弱い立場となりがちなパートタイム労働者や有期雇用労働者を保護するうえでの画期的な取り組みといえるでしょう。
もっとも、パートタイム・有期雇用労働法は、正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者の給与等を形式的に同一とすることを求めているわけではなく、禁止されるのはあくまでも「不合理な」待遇差です。
なにが「不合理な」待遇差であるかの判断は、企業にとって容易なことではありませんが、すでに、中小企業も含めてパートタイム・有期雇用労働法は全面施行されています。支援ツールや相談窓口を有効に活用しながら、正しい判断を行うことが必要です。

日本初のフリーランス向けファクタリングサービス
「FREENANCE即日払い」
会員登録自体は通常1時間以内で完了。会員登録を申し込んだその日に即日払いを利用することも可能です。
https://freenance.net/sokujitsu
▼あわせて読みたい!▼

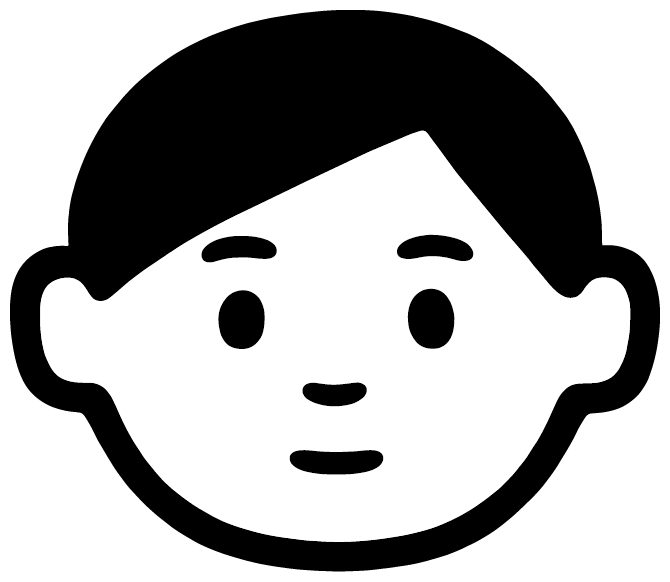 FREENANCE MAG
FREENANCE MAG 


