チェーン店ではない、“街のお店屋さん”。長年の営業で培った商品知識や仕入れ・販売の知恵、お客との交流を通して記憶された地域の歴史は、こうした個人商店にしか求め得ないものといえるでしょう。そんなお店を見つけ、通い詰め、店主に話を聞いて書き上げられた一冊が『絶滅危惧個人商店』(筑摩書房)です。
著者は、大阪の風俗街・飛田のルポルタージュである『さいごの色街 飛田』(筑摩書房/新潮文庫)を筆頭に、多くの著書を発表してきたノンフィクションライター井上理津子さん。キャラクターが立ちまくった店主たちが語る色とりどりの個人史は、戦後80年弱の現代日本史の一断片でもあります。
フリーランス35年のベテランである井上さんに『絶滅危惧個人商店』のことはもちろん、ご自身のキャリアについても伺いました。
日本文藝家協会会員。奈良市生まれ。大阪のタウン紙『女性とくらし』編集部勤務後、フリーランスに。雑誌『月刊SEMBA』を皮切りに、“来るもの拒まず”でやっているうち、「旅と味」「女性」「人権」が3本柱となり、紙媒体で主に執筆。一時期は生活環境文化研究所の外部研究員も務め、人物インタビューやルポを中心に活動を続けている。最近のテーマは、「墓」「仏教」「大衆文化」そして「本屋さん」。代表作に『さいごの色街 飛田』『葬送の仕事師たち』など。長く大阪を拠点としていたが、2010年から東京在住。
https://twitter.com/yasaio
https://inoueritsuko.com/
お店を選ぶ基準はハンサムな「現役感」
読んでいると、生き生きとしたお店の様子が目に浮かんでくるようでした。取材はどのようにされましたか?
ひたすらメモを取りましたね。録音は、断られたり警戒されたりする場合もありますし。わたしは発言の内容と同じくらい、ちょっとしたしぐさや表情が大事だと考えているんですけど、後々、原稿にするときに困ってしまうこともあって。例えば、東京・神田の豆腐の越後屋さんは、重たいものを持ち上げるときに、言葉で表せないような声を出して気合を入れるんですよ。メモには「けものの声」って書いていたんですけど、さすがに自分でもどうかな?と思って表現を変えました(笑)。
もともとは雑誌連載だったそうですが、井上さんご自身が企画されたんですよね。
はい、そうです。企画のきっかけにもなった、大好きな阿佐ヶ谷の文房具屋さんには「いやいや、恥ずかしいから無理よ」って取材を断られちゃったんですけど。転居した今も、文房具だけはそこに買いに行っています。
取材が終わった後もご愛顧されているお店がある?
アクセスの問題でなかなか行けないお店以外は、今も引き続き通っています。ついこないだも亀有の栄眞堂書店に寄ってきたんですが、品揃えがますます渋くなっていた。この本を「20冊売りましたよ!」って教えてくれて、ぐだぐだとお話ししてきました。取材でのご縁をこれからも大切にしていきたいです。どこも素敵なお店だから、自然に。

あとがきには「営業歴が長そうで、なんだか味があり、街に溶け込んでいると推察する」お店を取材したとあります。
この企画をやりたいと言った時点で、何軒かはイメージしていたんです。わたしは街をウロウロするのが好きなので、いい外観のお店に出会うから。連載が知られていくにつれて「あそこに行きなよ」と教えてくれる人もいて。ネットにはあまり情報が出てこないようなお店ばかりだから、実際にお買い物をしてみたりしてね。
いい外観というと?
関東大震災以降に作られた、正面だけ洋風に装飾された木造建築。いわゆる「看板建築」が好きなんです。本の裏表紙に描いてもらったイラストは、練馬駅前にある看板建築のお店をモデルにしています。基本的には、古い侘びた感じが好きなんですけど、あまりにも厭世的というか「掃除は10年してません」みたいなところは苦手。しっかり現役感があって、外観もちゃんと丁寧に磨いてあるお店に引き寄せられますね。
そういうハンサムなお店を見つけると「ごめんくださ~い」と入っていって……。
取りあえず何か買うんです。ボールペンや傘なんてどれくらい買ったかわからない(笑)。そうして店内の様子やご主人の雰囲気を観察して……。ちょっとイヤらしいですけど(笑)。
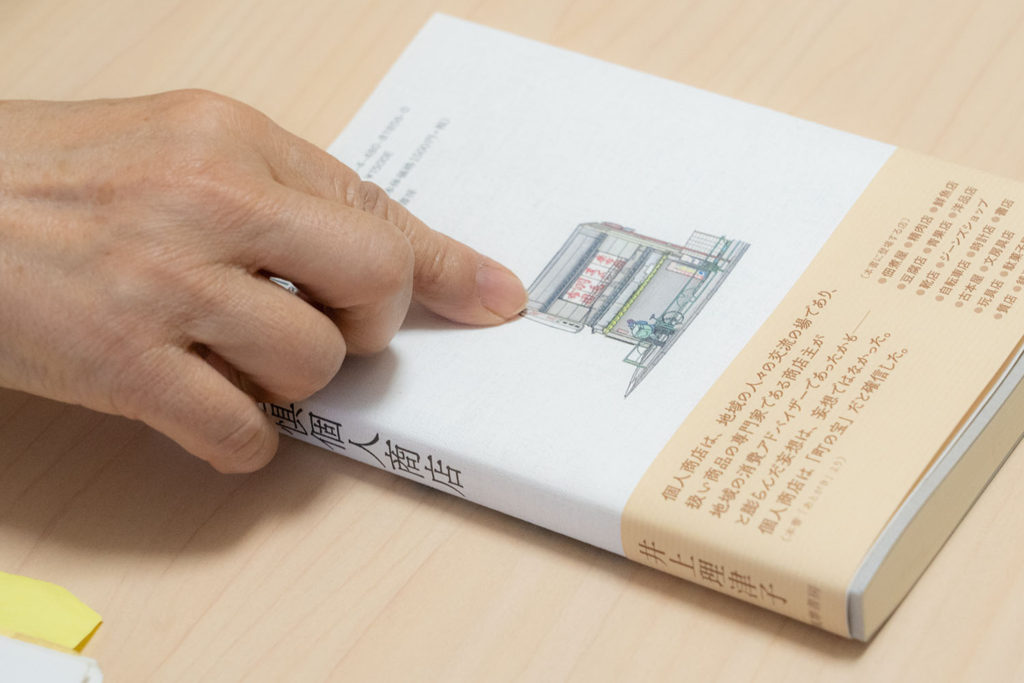
あえて脇道にそれることの大切さ
文房具屋さん以外にも、取材を断られたお店はありましたか?
多かったですよ。今のご主人から9割まで話を聞いて、あとは先代のおじいちゃんだけ、というところで新型コロナが感染拡大。「外部と接触させたくない」と言われてダメになっちゃったこともありました。あとは、連載がもう一回あれば取り上げたいと思っていたお店があって。書籍化にあたって追加取材できないかと連絡したんですけど、ご主人の認知症が進んでしまったそうで。「もう難しい」と言われてしまいましたね。
あとがきによると、掲載されているすべてのお店が今も元気に営業されているそうで、ホッとしました。
すごいでしょう? 日暮里の佃煮の中野屋さんなんて取材時は95歳ですよ。神保町のミマツ靴店さんも、93歳だった1代目が取材後に施設に入られて。息子さんが「父の話を聞いといてもらえてよかった」と言ってくださいました。
本にするとき、編集さんが取材したお店に連絡をとってくれたんですが、池上の駄菓子の青木屋さんだけ、電話がつながらなかったんです。郵便物も戻ってきてしまって。まさかとお店に直接行ってみたんですね。そうしたらお元気でいらした。「脚を骨折したので、1カ月ほどお休みしていたけど、もう治ったわよ」と。郵便物が戻ってきたのも単なる書き間違いでした(笑)。その翌週から営業を再開されて、本当によかった。
僕は青木屋さんのエピソードが一番好きなんです。本筋とは関係のない描写が豊かな余韻をもたらしていて。
ありがとうございます。「サラッと書いたように見える」ってよく言われ、嬉しいんですが、実はけっこう練っています。雑誌連載だから文字数が決まっている。流れを考えながら書き始めて、終わりが見えてきたときに必ず一回筆が止まるんです。どれを残してどれを切るか、悩んで迷って……。そのうちに「そうだ、これだ」みたいな方向性が出てくるんですね。

ご苦労なさったことはありましたか?
わたしは「楽しい」ばっかりでした。東京に来てまだ10年ちょっとなので、街のことをあんまり知らないんですよ。だから、再度お店にお邪魔するときは必ず古い地図を持っていったんです。お話を聞きながら「それってここですか?」と指し示すと、ご年配の方はめっちゃ喜んでくれて。「そうそう! 懐かしいねえ。実は……」と、いろんな話を聞かせてくれる。どちらかというと、編集さんが苦労されたと思います。わたしが遅筆だから(笑)。
西荻窪の須田時計眼鏡店さんも強烈でした。常連のお客さん同士が戦時下の話で盛り上がっているのをガッツリ盛り込んであって。脇道といえば脇道なんですが、すごく印象的でしたし、お店の雰囲気が伝わってきました。
そういったエピソードが、お店のあり方の象徴なので、書き入れたかったんです。須田時計眼鏡店さんは「毎日誰かが来ていて、ずーっと笑い声が絶えないお店」と教えてもらって。行ってみたら「紹介してくれるのはいいけど“絶滅危惧”ってタイトルでまとめられるのはイヤだ」って頑なに辞退されたんです。しつこくアプローチしたらなんとかOKしてくださいましたけど。本になるときに、もうひと悶着ありましたね(笑)。
駆け引きはお上手そうですが。
最初はだいたい迷惑がられるんですよ。当然ですよね。なので、そこにどう入り込んでいくか。お店の責任者が2人いらっしゃるとき、1人はOKだけどもう1人がイヤ、っていう場合もありました。でも、そういう状況だと、わたしは燃えるんです(笑)。「おっと、そうくるか。だったら次はこっちから投げてみるか」と、あれこれ工夫して。口の重い人がしゃべり出してくれたときって、たまらなくうれしくないですか?
確かに! ライター冥利に尽きるということですね。

「女性の自立」を肌で感じてフリーランスへ
井上さんご自身についてもお伺いしたいんですが、大阪のタウン紙の編集部にいらしたんですよね。独立されたきっかけは?
『女性とくらし』というタブロイド判16面のタウン紙を作っていたんです。企業に買い取ってもらって、社内でOLさんに無料配布するような。
タブロイド判16面を埋めるのは大変だったのでは?
半分ぐらいは記事広告だったかな(笑)。いい時代でした。そのころ、ある企業の取材で対応していただいた広報の方が当時としては珍しく女性で、しかもご年配だったんです。取材後に雑談をしていたら、その方が「わたしがなぜ働いているか」を話してくれて。いわく、夫さんが大学教授だったんだけども、急死された。義理の母と同居していたので、亡くなった夫さんのご兄弟に「生活費はわれわれがもつから、母の面倒をよろしく」って言われたそうなんです。だけど、「そうしてお金をもらって暮らしていると、いつまた同じことが起きるかわからない。だから自分が働くことにした」と。

「女性の自立」ですね。
はい。まだ男女雇用機会均等法の施行前でしたからね。その方がおっしゃったのが、「もし夫が急死しなかったら世間を知らないままで、ずっと暮らしていたと思うけど、こうなったおかげでいろんな経験ができてよかった」。その言葉にいたく感銘を受けまして、市井で働いてきた女性にインタビューして本を作りたくなったんです。それで、1984年に会社を辞めてフリーランスに。翌年に共著で『女・仕事』(長征社)を出しました。
なるほど。
バブル時代は、おいしい仕事もありましたねー。しかも当時は結婚していたこともあり、認識が甘かった。これがこのまま続くと、なんの根拠もなく思い込んでいましたね(笑)。
フリー当初の寄稿先は『大阪新聞』(2002年廃刊)と『月刊SEMBA』(1996年休刊)が2本柱でした。その後、地元大阪の仕事では、府立ドーンセンター(男女共同参画・青少年センター)の本作りをしたり、当時は大阪市の外郭団体が発行していた月刊誌『大阪人』(2012年休刊)に連載したりしていました。『月刊SEMBA』の編集長だった廣瀬豊さんがわたしの恩師です。
廣瀬さんからはどういったことを教えてもらいましたか?
すべてですね。取材の姿勢から、原稿の書き方から。漫画評論をやっている同業に、わたしと同じく彼の薫陶を受けた中野晴行さんがいますが、その中野さんと、廣瀬さんのでっかいポートレートを行ったり来たりさせています。お互いここぞという時に廣瀬さんの力を借りるために。今はウチにあります。『絶滅危惧個人商店』のまとめのときもそれを仕事部屋に置いて、睨んでもらいながら仕事をしました(笑)。アホみたいでしょ?
そんなことないですよ。文字通りのお目付役。
「こう書いたら廣瀬編集長はなんて言うか」といつも気にしながら仕事しています。そんな存在に出会えたことは、とても幸運でしたね。

フリー25年で大阪から東京へと移る
2010年に東京にいらっしゃったとのことですが、フリー25年を目前にして、50代であえて拠点を変える人は少ないと思います。
メインで書いていた『大阪人』に元気がなくなってきていた時期で、他に関西で書きたい媒体がなく、仕事が減って来たのが一番大きかったです。7割がた東京の媒体の仕事で食べていました。子どもたちもほぼほぼ独立したし、ちょっと行ってみようと。
あと、ちょうど『さいごの色街 飛田』の執筆中だったんです。『絶滅危惧個人商店』と同じ編集さんなんですけど、「井上さん、このまま大阪にいたらいつまでたっても書き上がらないよ」って言ってくれて。飛田は現在進行中の街だし、近いから何度も通ってしまって、キリがないんですよ。そこで「そうですね、はいはい!」ってノコノコと東京にやって来たら水に合ってしまいました(笑)。
フットワークの軽さはぜひ見習いたいです。井上さんがお仕事を通してもっとも伝えたいことをお伺いできますか?
そういえば、社会学者の上野千鶴子さんと著書を交換しているんですけど、『絶滅危惧個人商店』をお送りしたときは、いただいたハガキに「あなたはよほど無くなっていくものが好きなんですね」って書いてありました(笑)。わたしが伝えたいことはなんだろう……? 例えば、『絶滅危惧個人商店』に登場する人たちは、お店をやっていることで「社会と契約している」と思うんです。
社会の中での居場所というか、役割みたいなものを得る媒介として、お店があるということでしょうか。
そうです。以前、『関西名物・上方みやげ』(創元社、共著)という本を出したときに、兵庫・西宮の清左衛門さんという佃煮屋さんの成り立ちを伺ったんですよ。先代のお母さんが、大阪で料理屋をやっていた親戚に「みやげもん作って」と言われて、家で作っているのをそのまま出したらすごくウケた。阪急百貨店のバイヤーが買いに来て、お膳立てされた格好で店舗を構えるようになったのが始まりなんです。あくまで趣味的な感じで始めたので、営業時間もきちんと決めてなかったんですって。今の時代では考えられないでしょうけど。
それでも売れたぐらいおいしいんですね。
そうなんですよ。むちゃくちゃおいしい。ところが営業時間を決めずに気ままにお店をやっていると、あるとき、お店を開けていない時間にお客さんが来て「両親に食べさせたいから、今から田舎に持って帰りたいのに、買えないのか」と言われた。そこから「個人商店といえども、社会との契約なのだから」と、お店をやることに対する認識を改めたそうなんです。そのお話をとてもよく覚えていて。
清左衛門さんのようなきっかけがなくても、長い年月のうちにいろいろな経験をしてきて、これは仕事であって社会との契約である、と認識して皆さん日々お店を開けてらっしゃるんだと思うんです。いってみれば、こうした小さな「人の営み」が積み重なって、街という大きな歴史ができあがってきたんだと。
ともすれば見過ごされてしまう市井の人々の営みを記録し、伝えていくということですね。
わたしは、普通の人が好きなんです。「美は細部に宿る」とかいいますけど、それにこじつけると「真実は“微”に宿る」ような気がするんですね。例えば、ふとしたときのさり気ないしぐさや、雑談の中で何気なく発する言葉。そういった微かな部分に、その人の本心みたいなものがにじみ出ているように。いちライターとして、それを聞き出したいなっていう思いを持って、今日も街を歩いています。

撮影/阪本勇(@sakurasou103)

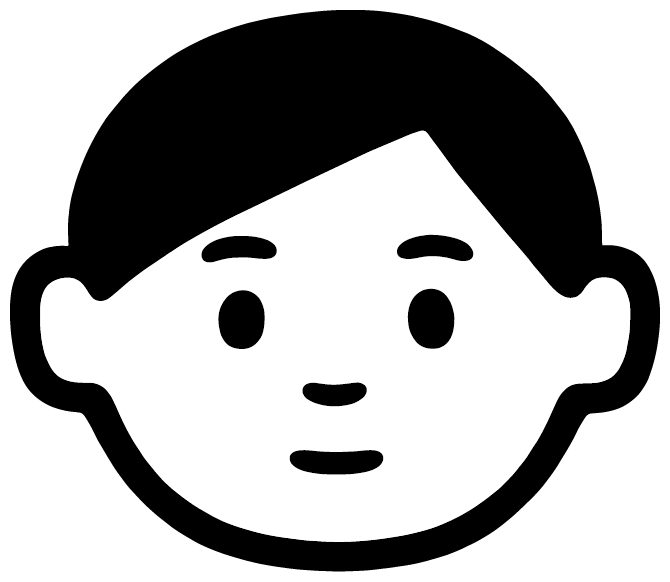 FREENANCE MAG
FREENANCE MAG 


