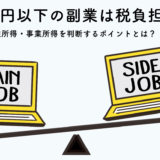人とのコミュニケーションがあってこそ

ところで牟田さんはお子さんのころからずっと本好きでいらしたんですか?
読んではいましたけど、それしかやることがなかっただけで、好きかといわれるとどうなのかな?と(笑)。親がわりと厳しくて、おもちゃは買ってくれないし、テレビも見せてくれなかったんですよ。
社会人の第一歩が図書館員で、のちに校正のお仕事をされることになるのに?
図書館って「本が読める職場」みたいなイメージがある人が多いと思うんですけど、わたしはそれよりも、いろんな人が本を読んでいる姿に惹かれたんですよ。図書館員として担当していたサービスもレファレンスとか、貸し出し/返却や予約リクエストの窓口で、ずっと本に触っていたいとか、選書がしたいとかはそんなに思わなかったんです。
職場に行けばもちろん本は触りますし、選書も任せてもらえたし、知らない本を読むのも面白かったんですけど、本とだけ付き合っていたいとは全然思いませんでした。結局、サービスする相手は本じゃなくて人なので、人が好きじゃないと務まらないと思います。校正の道に進んだのも、当時もう30歳でしたし、まったく何もわからない世界に行くよりは、図書館での経験が多少なりとも生かせるんじゃないかと思ったからで、完全に成り行きなんです。
本というより、人とのコミュニケーションへの希求が強かったのかもしれませんね。お師匠さんが《迷ったとき、一度入れた鉛筆に粗く消しゴムをかけあえて痕跡を残すこともある》とおっしゃったというエピソードを思い出しました。なかなか高度なコミュニケーションだな、と(笑)。
校正の仕事って、ずっと紙と向かい合っているように傍からは見えるかもしれませんけれど、実際には著者とコミュニケーションを取らなきゃいけないし、それ以上に編集者との意思疎通が大事ですからね。
おたずねをするにしろご提案をするにしろ、書き方ひとつで伝わり方は大きく変わりますし。わたしだけじゃなく、経験の長い人たちはみなさん「伝え方」にはすごく気を遣っていらっしゃると思います。入れた鉛筆を検討していただけるように、きれいに書こうとかわかりやすく書こうとか意識しますし、編集者の話をしっかり聞いて「こういう本にしたい」というゴールをちゃんと確かめておかないと、いい仕事はできませんから。

やっぱり本そのものがフェチ的に好きというよりも、本を通してのコミュニケーションにご関心があったんですね。
そう思います。本ってやっぱり必ず読者がいるものですからね。みんなで一所懸命作るからには、必要とする読者に届いてほしいし、読まれてほしいじゃないですか。そう考えたら、わたしは売れ行きにも無関心ではいられませんし。
でも、そういうことを考えるようになったのは、出版の世界の大先輩たちのお話を聞いてきたからで、自発的だったわけではないと思うんです。いまでも人としゃべっているといろいろ考えるけど、ひとりのときは意外と考えないみたいな(笑)。たまたま夫も同じ仕事をしているので、その日にあったことやいまやっている仕事のことを話したりして、それで考えるということもありますけれど。
おしゃべりはお好きなほうですか?
仕事で会う人で気が合うとけっこう話し込みますけど、友達は全然いません(笑)。近年は好きなものや興味・関心のあるテーマが共通している人たちと展覧会でバッタリ会ったりとか、知り合いの知り合いだったりとかで、ゆるくつながることが増えました。そうして面識のある方からご依頼いただいた仕事を、日程が空いている順にお引き受けしているだけで、けっこういっぱいになっちゃいます。
すばらしい! 理想ですね。
いやいや、書籍の校正ってけっこう時間がかかるので、ひと月に頑張っても2、3冊しかできないんですよ。ライティングとか編集とか写真のお仕事と比べると圧倒的に本数が少ないので、キャパが小さいだけなんです。
失敗は許されないが、常に失敗している?

文脈や曖昧さを大事にされる牟田さんの考え方は、《校正者は「事実としては、こうではありませんか」と指摘はします。採る/採らないは編集者と著者しだい》といった記述に表れている気がします。
ある作家の方が「校正は注意喚起をしてくれるから助かる」とおっしゃっていましたが、わたしもそれでいいと思うんです。「この部分の言葉がちょっとわかりにくいので、こう書きかえたり、いいかえたりしますか?」とゲラの上でおたずねはしますけど、別に採っていただけなくてもよくって。
こちらもそれがベストだと信じて指摘や提案をしているわけではないので、本当に注意喚起だなと思うんですよね。「もう一回、検討してくださいね」という役割でもあると思っているので、鉛筆に従わないで第三の道を行っていただいても、わたしは全然かまわないと思っています。それで読者にとってよりよい本になるのなら、それが一番ですから。
あと、これがいちばん刺さったんですが、《失敗は許されないが常に失敗しているという矛盾した仕事が校正であるともいえるのではないでしょうか》という(笑)。どんな達人でも絶対に見落とさないということはないし、しかもないということは証明できないというつらさ。
人間は絶っっっ対にミスをしますからね。誰が見ても明らかな誤字脱字じゃなくて、見る人によって答えが異なる場合もあるから、誰が見てもいっさい何も気にならない本なんて、たぶんないと思うんです。でもわたしたちの仕事は絶対に間違いを見逃してはいけないというか、看板にはそう謳わないといけないわけです。「何か落としているかもしれませんが、頑張って拾います」という看板ではやっぱりダメなので(笑)。
厳しい仕事だなとあらためて思いました。商品や製品を作るというのは本来そういうことなんですけれど。
書籍は誤植が出ても「すみません、重版で直します」で許されちゃうところがありますけれど、例えば新聞の校閲記者なんて、日々あれだけ広範囲にわたる膨大な量の情報を限られた時間で校閲なさっていて、かつ部数も桁違いだから、ものすごい数の衆目にさらされて、間違いがあれば指摘されまくり、訂正を出して頭を下げていらっしゃる。それに比べたら自分なんか全然なんてことないなと思います。
特にいまの世の中、間違いに異常に厳しいですよね。
それは本当につらいというか、「これでいいのかな」といつも思っていることです。この仕事をしていれば「辞書によればこれはこうです」と断言できるようになるのかと思いきや、やればやるほど歯切れが悪くなっていくんですよね。「雨模様」を雨が降る前という人もいれば、降った後だと思っている人もいるし……とか、「敷居が高い」はもう「ハードルが高い」でいいんじゃないですかね……とか(笑)。

辞書にしたって、「この辞書ではAだけど、この辞書ではBだし」って迷うし、正しさを振りかざしてしまうと、聞いてもらえる話も聞いてもらえなくなるみたいなこともあるし。なのでわたしは「正しい」という言葉は自分では使えないな、と最近は思っています。「この辞書によれば」とか「この資料によれば」はまだいえるかもしれないけれど、「これが正しい」と自分ごときに断言できる物事なんて、世の中にはそんなにないと思うんですよ。
そういう歯切れの悪さって面倒くさいし据わりが悪いから、「どれが正しいのか、はっきりしてほしい」と思う気持ちはわからなくはないんですよ。いきおい、正誤の論争が過激になったり、間違っていると思った人や物事を必要以上に厳しく断じてしまったり。それは見ていて非常に苦しいですね。もうちょっと寛容に……といったら弱腰に聞こえるかもしれませんが、「これが正しい」と声を張り上げる前に一瞬立ち止まって、本当に正しいかどうか、書物をひもといてみるとか辞書を引いてみるとかまわりの人と話すとかして、ちょっと考えてみてもいいんじゃないかな、と思います。
「専門家が間違えるなんてありえない!」とかね。人間だから間違えることはありますよ、というのが社会的合意になってくれたらいいんですけど。
地道にでもいいつづけていくしかないんでしょうね。それぐらいしか自分にできることはないかなと思います。いきなり「これが正しい」といってしまうことに自分だけは乗っからないことと、「ちょっと考えてみませんか?」と、ちっちゃい声ででもいいつづけること。そういう意味では本を書けたのはよかったかなと思っているんですけれど。
「目を替える」意味

そう思います。他に何か気になることはありますか?
「調べる」ということについてはいろいろ思いますね。もっともっといろんなやり方があるのに、Googleで終わっちゃうのはもったいないなって。図書館で調べるのは誰でもできることじゃないにしても、いまは1000円ちょっと払えば国語辞典をスマートフォンに入れることもできるし、ネットで無料で引ける辞書もあるのに。
わたしはインターネットを悪いとはまったく思っていないんですよ。むかしだったら国会図書館まで行かなきゃできないような調べ物が誰でもすぐできるって、すばらしいじゃないですか。ネットだってまだまだ使いこなせるし、面白いんですよ。だけど、その面白さがまだあんまり知られていない感じがして、これももったいないなと思います。誰かの名前で検索して、たくさん出てきた記事の中から、どれがちゃんと取材して書いたもので、どれが既存の情報をつぎはぎした適当なものか、ちょっと考えてみてもいいんじゃないかなって(笑)。
僕がひとつ気になるのは、ウェブ媒体の記事で校正をあまりにもしていなさすぎる文章をよく見かけることです。予算の都合もあるでしょうから校正を入れろとまではいえませんが、編集者はもう少し読んでもいいんじゃないのかな、と。
それはよく聞く話ですし、実際ありますけど、これは小声でいうんですが「いや~、本も……」と思うことも(笑)。ウェブでも、例えばLINE NEWSにはちゃんと校閲のチームがあるんですよ。noteでウェブの校閲について記事を書いて発信したりもしています。
編集者が校正者を兼ねるのって、やっぱり無理があると思うんです。この本を書いたときに、わたしも校正の仕事をしているので、一応見たんですよ。でも、プロの方に自分とは別の視点から見ていただくと、単純な写し間違いも、勘違いや思い込みで書いていた事実誤認もありました。「ここはこう読まれちゃうかもしれませんが、大丈夫ですか?」と指摘していただいて書き直した箇所もいっぱいあります。
校正のプロでなくても、同じ編集職でも隣の席の人に読んでもらうとか、それだけでもかなり違うし、実際そういう仕組みでやっているところもあると思います。そういう工夫をもうちょっとできたらいいなって思うんですけれど、みんな忙しすぎるんでしょうね。

目を替えることは大切ですよね。何回読んでも見落としていたミスが、本になってからあっさり指摘されるということも、残念ながらよくあります。
ありますよね~。理想をいえば、文字のあるところには必ず校正が入っていてほしいんです。すべてプロが見るのは不可能に近いと思いますけれど、校正の視点みたいなものを、できるだけ大勢の人が頭の片隅にでも持っておいていただけると、それだけでちょっと違うんじゃないかな、とは思いますね。迂闊に断定してしまうことの怖さとか、参照する資料をちゃんと見極めることの必要性を、みなさんがもうちょっと知っていてくれれば。わたし、最近は人の名前は絶対に自分でタイプしないですもん。全部コピペします。
あ、そうか。名前って意外と間違えますもんね。
意外と間違えるし、意外と失礼になっちゃうじゃないですか(笑)。間違いが発生しやすいわりに深刻な事態になりやすいから、「みんな、記事でもメールでも人名はコピペしたほうがいいよ!」っていいまくりたいです。簡単にできることですしね。
そのお話はすごく有益ですね。
「牟田郁子さん」があまりに大量に発生しすぎていて、「コピペしてくれ!」って思いますもん(笑)。パッと見で「都子(さとこ)」を「郁子(いくこ)」って思い込んじゃう人が多いのかな。わたしは全然かまわないんですけど、「傷つかない気づき方をしてほしいな」とか思います。指摘されたら恥ずかしいじゃないですか。正しいことをいわれると、人は傷つくんですよ。
わかります、わかります。
いかに相手を傷つけないで気づいてもらえるようにうまく持っていくかに、わたしたちは日々こんなに心を砕いているのに、みんなひとつ情報が間違っているぐらいでキーッとなって(笑)。もう、つらいですよ。
本当につらいですね……。
校正をすると人に優しくなると思います。
(笑)。校正をすると人に優しくなる。本日のパンチライン、いただきました!
みんな本当に一所懸命考えて書いて作っているけど、人間が作っている限りどうやったってパーフェクトなものはできないんですよ。なのに、本当にわずかな瑕疵を「ひどい欠陥品だ!」みたいにいいたてられると、しょんぼりしちゃうじゃないですか(笑)。それで記事とかメディア自体がなくなっちゃったら、みなさんも寂しいですよね?って。お互いに優しくなりたいですよね。

撮影/中野賢太(@_kentanakano)

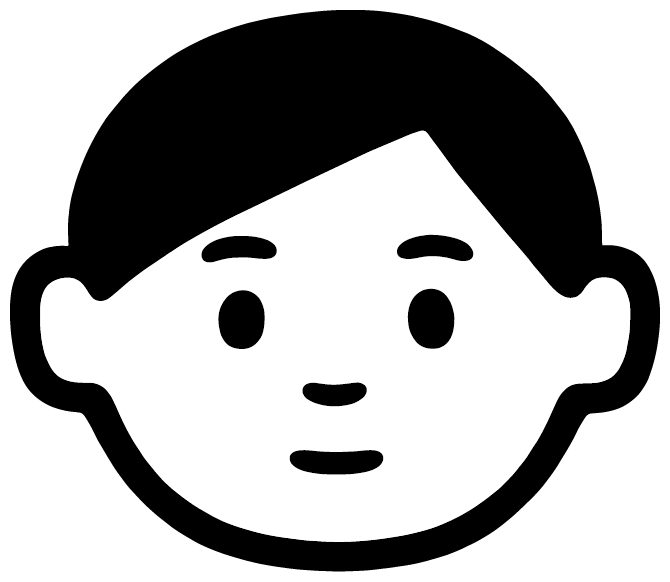 FREENANCE MAG
FREENANCE MAG