とみさわ昭仁さんの新刊『勇者と戦車とモンスター 1978〜2018☆ぼくのゲーム40年史』は、1961年生まれの著者が高校時代、当時大流行したビデオゲームのはしり『スペースインベーダー』に出会うところから始まります。
漫画家、イラストレーターに挫折し、歌謡ミニコミ誌『よい子の歌謡曲』への投稿をきっかけにフリーライターになり、ファミコン好きが高じて攻略記事を書いたりしているうちに、田尻智さんと出会って株式会社ゲームフリークの立ち上げに参加。『ポケットモンスター 赤・緑』をはじめとするゲームの制作に関わるも、そこで落ち着くことなく、フリーに戻ったり、古書店『マニタ書房』を開いたりと、まさに波瀾万丈の半生を、この40年のテレビゲームとその業界の変化に重ねて描いた、抜群に面白い一冊です。
会社勤めをした時期もあったものの、基本的にはフリーランスとして生計を立ててこられたとみさわさんの人生と考え方について、じっくりとうかがいました。
1961年、東京・両国生まれ。ゲームや映画、古本、音楽などに精通し“プロコレクター”“日本一ブックオフに行く男”“アレコード蒐集家”として知られるフリーライター。著書には、自身のコレクション論を綴った『無限の本棚』(アスペクト/ちくま文庫)など。『メタルマックス』『マリオとワリオ』『ポケットモンスター 赤・緑』など多数のゲーム作品の制作にも携わる。
https://twitter.com/hitoqui_ponko
https://suzuri.jp/hitoqui_ponko
ゲーム業界の観察者という視点

表紙イラストは、漫画家・鈴木みそが担当
帯の文言にもありますが、まさに波瀾万丈の人生ですね。
波瀾万丈っていうと運命に翻弄される感じがありますけど、僕の場合は自分から招いているというか(笑)。あんな優良な会社やめなきゃいいのにやめちゃうんだから、自分のせいなんですよ。
「序章」に《ぼく自身は天才でもなんでもない凡人だが、天才と出会ってしまう才能だけはあったのだ》とありますが、これがご自身の40年を総括する感慨に近いのかなと思いました。
そうですね。運がいいって言うとあれだけど、自分から何かしたことがあるとすれば、面白そうなところにいつも首を突っ込んできたことぐらいなんですよ。それが仕事になるならないは関係なしに。その結果とは言えます。
僕はゲームに疎いので、よくわかったのは『よい子の歌謡曲』のことぐらいだったんですが(笑)。
水道橋博士のメルマガ『メルマ旬報』の連載が元になっているんですけど、書籍化にあたってゲームに関わる前の話はちょっと削りました。
僕のゲーム史だから、『よい子の歌謡曲』に参加して芸能ライターを始めて、その周辺のあれやこれやと付き合ってるうちにファミコンブームがきてゲームライターになって……という流れからずっと書いていたんだけど、駒草出版さんで書籍化していただくときに、もう少しゲームに話を絞って、業界の流れや、何が流行っていたのか、どんな状況の中でどういうふうにゲームや雑誌が登場して、僕がどういうふうに立ち回ったのか、というのがわかるようにしましょうと言われて、僕もその通りだなと思ったので、個人史的な部分は少し刈り込んだんですよね。

先ごろ亡くなった水島新司先生の『ドカベン』の柔道編を短縮したような感じですね。
そうそう(笑)。『ドカベン』も最初から野球漫画にするつもりだったらしいじゃないですか。僕も最初からゲームの話を書くつもりだったので同じですね。恐れ多いけど。
同じような場所にいて、同じような経験をした人はきっと他にもいたと思うんですが、とみさわさんがこういった道を歩まれたことには、やっぱり固有の理由があったんじゃないですか?
ゲーム一途じゃなかったからですかね、言われてみれば。ゲームフリークに入社するときもためらったし、やっぱり文章を書くことが好きだったから、どうしても気持ちがそっちへ、そっちへ行くんですよ。仮に「ゲームの世界でトップになるんだ!」という気持ちが強かったら、そのままゲームフリークにいて順調に出世もしていたと思うんです。そこに僕は迷いがあって、退職してフリーライターに戻ったり、『桃鉄』を手伝ったりと、フラフラ、フラフラしていたんですよ。そのことが結果的に自分の人生を面白くしたなとは思います。
前にFREENANCE MAGに登場していただいた姫乃たまさんが、地下アイドルの世界に参与観察的なスタンスで潜り込んで本を書いていたのを思い出します(※)。順番的にはとみさわさんのほうがはるかに先ですが。
※フリーランスは「やりがい搾取」の対象!? 深井剛志弁護士×姫乃たま『地下アイドルの法律相談』対談(後編)
確かにゲーム業界の観察者みたいな部分は少しはありました。僕は別に記憶力がいいわけじゃないんですけど、メモ魔でコレクターだから、いろんなものを取っておいたり日記をつけていたり、自分年表まで作っているんですよ。そのおかげでこういうものが書けたという。
観察者という意識は最初からありましたか?
いや、わりと後半ですね。ゲームフリークには2回入社して2回退職してるんですけど、最初に所属したころはわりと夢中でした。やっぱり天才(ゲームフリークの創業者である田尻智氏)と出会ってしまったから、「こいつの片腕になって世界に広める手伝いをするのも悪くないな」と思った時期はあります。そこで自分の限界を悟って会社をやめたんですが、もう一度頭を下げて会社に戻ったときは観察者気分がありました。僕がいない間に会社がグンと大きくなったから、自分がいたころとの差があるわけですよ。それはいったん外に出たからこそ見えるものでしたからね。
組織が成長する過程を現場にいた人の視点から綴った本ってどれも面白いですが、そういう側面もあるかなと。
僕もそういうノンフィクションやドキュメンタリーが好きなので、多少は意識しました。自分は「ゲームフリーク史の語り部のじじい」でいいかな、って気持ちはあります(笑)。会社にいたときも出版部の主任を務めていて、社員旅行のアルバムを編集したり、社内報を創刊したりもしていましたから。
消去法からライターの道へ

そういう役割が回ってくるのは、やっぱりお好きだから?
あると思いますね。子どものころ壁新聞とか作っていましたし。よくある怪獣の絵を描いて半分に割って内部図解をするみたいなのも好きだし、迷路を描くのも好きだし。
小さいころから手を動かすのがお好きだったんですね。
それが若いころは絵だと思ってたんですけど、途中から「そうでもないな」と限界を感じて(笑)、活字のほうに進みました。
文章を書き始めたきっかけが西村寿行というのが面白かったです。
意外でしょう(笑)。でも、西村寿行をちゃんと読んでいる人であれば、おそらく僕の本を読んだらわかると思うんですよ。あの人の文章ってすごく歯切れがいいんですよ。僕はそれにしびれて、自分もなるべくテンポがよくて読みやすい文章を今も心がけています。
小説に挑戦したこともあって、一回だけ300枚ぐらいの長編を書いてあるところに応募したんだけど、箸にも棒にもかからなくて、「俺はこっちの才能はないんだな」と思い知らされました。でも取材して読みやすい形にまとめるのなら勝負できるかもしれないな、と思って、今に至るんですけどね。

ハードコアチョコレートが制作した「ナスカジャン」
絵から文章に転向したのはどういう理由で?
望月三起也の『ワイルド7』に憧れて模写ばっかりしていたんです。ただ憧れた相手が悪かった(笑)。圧倒的にうまい人ですから、自分の線がダメでダメで、漫画家は無理だなと思ったんですよ。その少し後に『よい子の歌謡曲』と出会って夢中になって「ここに参加したい!」と思って、学校の作文なんて大嫌いだったのに、見よう見まねで歌謡曲のレビューを書いて投稿したら、何回めかで掲載されて。それから編集部に遊びに行って、ズルズルとこの道に入っていっちゃうわけですね。
作文が嫌いだったのに書いてみようと思われたんですね。
かっこいいことを言えば言えるかもしれないけど、本音を言うなら、絵に挫折して「文章ならなんとかならないかな?」っていう消去法ですよ。『よい子の歌謡曲』時代に書いた原稿は全部燃やしたいです(笑)。なんとかマス目を埋めようとしてつまんないギャグで水増ししていたり、もうヘタでヘタで。
そのころは歌謡曲評論でなんとかなりたいと思っていたんですよ。というか、それしか思いつかなかった。他のことが書ける気がしないし。知識も教養もない、読書家でもない。でも歌謡曲は聴けるじゃないですか(笑)。3分間黙ってりゃ耳に入ってくるから。書評をやろうと思ったら本を読まなきゃいけないですから。……すごく音楽をナメた発言ですけど(笑)。
面白いのでそのまま載せておきます!
『よい子』はアイドル雑誌でもあったから、楽曲分析でなくても、アイドルのかわいらしさを文章で表現するとか、いろんな切り口がありますしね。堀ちえみの「ジャックナイフの夏」という曲のレビューを、タイトルと歌詞から思い浮かんだストーリーをショートショートみたいにして書いたこともあります。ミニコミだから許された部分もあったでしょうし、勉強の期間だったと思います。
そこにファミコンブームがやってくるんですよ。ファミコンで遊んでいるうちにゲームの仕事が来始めて、そっちは頭を使うも使わないも、遊んで攻略法を記事にするだけだから、ゲームが好きなら誰でもできるっちゃできるわけですよ。しかも黎明期だからノウハウなんてないし、みんな手探りで。ある意味、いい時代でしたよね。それも文章の勉強になりました。
「面白いこと」が始まる匂い

同じ『ファミコン通信』の執筆者だった田尻さんと出会って、ゲームフリークに遊びに行ったときに《ぼくは痛切に「ここに加わりたい」と思った。「よい子の歌謡曲」に参加を熱望したときの衝動にも似ている》とあります。これがとみさわさんの人生をドライブしてきた気持ちなのかもしれないと思いました。
そうですね。『よい子』のときも、編集部に遊びに行ったら先輩のライターが面白い人たちだったんです。同じようにゲームフリークは田尻はもちろん、杉森(建)くんとか、他の人たちも面白いんですよ。仕事のないときは毎日のように会っては一緒に遊んで、メシを食ったり飲みに行ったりしていました。
赤塚不二夫さんや山下洋輔さんたちが夜ごとドンチャン騒ぎをしていたとか、あるいはもっと遡ればトキワ荘のグループとか、何か面白いことが始まるときの集団の感じに僕は憧れて育ってきているから。そういう梁山泊的な匂いを僕は『よい子の歌謡曲』にも嗅いだし、ゲームフリークにも嗅いだんですよ。
そして田尻さんたちと一緒にいろんなゲームを作っていくことになるわけですが、彼は天才だ、俺はどうなんだ、という具合に、観察と比較の視点が入ってきますよね。一体化はしないで、少し引いた視点から見ている感じがあります。途中で「ついていけてない」と思ってやめちゃったりとか。
自分で勝手に自分をジャッジしちゃうんですよね。小説や漫画に行ききれなかったのもそれだと思うんですよ。創作者になるような人って、ヘタだろうがやめろと言われようがひたすら書くじゃないですか。僕は途中で自分で「無理だな」ってジャッジしちゃう。そういう人はいちばんダメなんですよ(笑)。

資質としては批評寄りなんでしょうね。
そう思います。それはだいぶ歳をとってから気がつきました。
フリーになったり勤めをしたりしながら、一時はそうとう稼いでいらしたわけですよね。
ゲームフリークを一回やめていた期間に、アスキー社から「2,000万円払うからRPGを一本作ってくれ」と言われて『ガンプル』を作ったときですね。でも、あれも2年ぐらいかけていますから。いちばん年収が多かった年が1,200万ぐらいでしたけど、そんなもんですよ。しかも僕はお金に無頓着だから、「やった!」と思ってバンバン使って、翌年か翌々年、ひどい目に遭いました(笑)。
だから僕はフリーランスのお手本にはあんまりならないと思うんですよ。その場その場行き当たりばったりで、ろくに貯金もしないで、立ち行かなくなって会社に泣きついて再雇用してもらうような、ひどい人間です(笑)。
そうおっしゃいますが、たくさん面白い経験をされて、面白い本をいっぱい書いてこられた時点で勝ち組フリーランスなんじゃないですか?
勝ち組とは思いませんけど、満足はしています。変な話、僕はもういつ死んでもいいやと思っているんですよ。仕事としては十分納得のいくものを作って書いてきたし、子どもも手が離れたし、女房にも先立たれているし。あとは余生で好きなことだけして暮らしていければいいなと思うんだけど、今の時代、物書きはなかなかそうもいかないですよね。
僕は雑誌が元気だった時代に仕事をしていたのと、ゲームフリークに在籍して『ポケモン』に関わったことである程度、名前が知られているので、今はさほど稼いでいるわけでもないけども、それでも署名のコラムの仕事とかちょいちょいいただけるのはそのおかげだなと思いますね。そこには本当に感謝です。
フリーランス、60歳の壁

2011年に創業されたマニタ書房を2019年に閉店されたのはとても残念でした。
2009年にゲームフリークを2度めの退職をして、『桃鉄』のさくまあきらさんのお手伝いを細々としていたときに女房が亡くなって、保険金が多少入ってきたので、それを元手に昔からやってみたかった古本屋をやったんです。そしたら出版界がまた注目してくれて、だんだん仕事が増えてきて「このまま自転車操業的にやっていけるかな?」と思っていたら、2018年の暮れに母が倒れてしまって。これは自宅で仕事をしなきゃダメだと思って店を閉じました。
幸い治療の甲斐あって、母は今また普通に動けるようになっているんですけど、古本屋は十分楽しんだからいいかなと(笑)。今は『メルマ旬報』で「マニタ書房閉店日記」を連載しています。
人生総括モードに入っていらっしゃる感が若干ありますね。
完全にそうですね。『無限の本棚』は僕とコレクションに関する自伝であり、『勇者と戦車とモンスター』は僕とゲームに関する自伝であり、「マニタ書房閉店日記」は……これはちょっと違うかな。古本に絞った自伝的な、たった7年間の日記です。今、準備しているのが子育てエッセイです。娘が産まれてから成人するまでの、コレクターによる、ゲームデザイナーによる子育て論(笑)。
結婚はしても子どもをもうけることには躊躇する人も多いですよね。
そんな話も書こうと思っています。僕も子どもを持つつもりは最初はなかったんですよ。女房が欲しがったから「まぁ、しゃあねえか」と思って(笑)。そのときちょうどアスキーから大きな仕事をもらえたから、子どもを持つというか結婚にも踏み切れた感じなんです。そのくせ、病身の女房とまだ小さい娘を抱えているのにゲームフリークをやめちゃうでしょ。竹熊健太郎さんにも『フリーランス、40歳の壁』(ダイヤモンド社)で取材を受けたときに笑われました。
僕個人は40歳の壁ってそこまで深刻ではなかったんですが、その問題に関してはどう思われますか?
僕もそんなに壁らしい壁はなかったんですよ。女房の病気はフリーランスであることとは関係ないしね。だから本では「いろんないい人との出会いで壁を乗り越えてきた」って言い方をしています。50歳のときも感じなかったんだけど、今、60歳になって初めて壁を感じていますね。露骨に仕事が減ってきている。
よく指摘されるのは、発注側が我々よりも若くなっていくことですね。
だって編集長どころか取締役と同じ世代ですからね(笑)。そりゃ若い編集者は僕みたいな年寄りの相手をしたくないですよ。僕は気が若いところがあるので、ギャップを感じさせないようにしてはいるつもりですし、新たに組んだ編集者にはすごく親切にしています。とにかくよけいな心配はかけない。締切は絶対に守るし、進行表を書いて定期的に見せて進捗を知らせたりしてね。

偉大です。読んだ方のご感想などはお聞きになりましたか?
安田理央くんは「この本はライター史でもあるね」と言っていましたね。その部分はさっき話した通り削ったから、そこをもっと膨らませればまた別の本ができるなと思いました。自分で読み返してみて思うのは、「ゲームとサブカル史」という切り口があったな、と。コンピューターゲームってこの世に登場したときはアンダーグラウンドなサブカルチャーだったんですよ。それがだんだんとオタクカルチャーになり、いまやメインカルチャーじゃないですか。そのきっかけのひとつが『ポケモン』だったりもすると思うんだけど。
そうして変わってきていることに気がついて、昨年末にDOMMUNEの宇川(直宏)さんに提案したら速攻で返事が来て、作家の渡辺浩弐さんと脚本家の佐藤大くんと3人で、今年2月に「40YEARS HISTORY OF TVGAME & SUBCULTURE」という番組をやったんです。1回で終わるかと思ったら話しても話しても終わらないので、「後編をやりましょう」って話になっていて。それも2回分終わったらまとめれば一冊になるんじゃないかと思っています。
とみさわさんはこれまでいろんなものにご興味を持ってこられたわけですが、その多くに共通するものって何だと思われますか?
僕ね、自分が好きなんですよ。よくナルシストって言われます。だからひとり遊びが好きで、ゲームも対戦ものにはまったく興味がない。『スト2』や『バーチャファイター』も一回もやらなかったしね。テレビゲームがすごいと思ったのも、『ドラクエ』が登場したときに「ひとりでこんなに豊かな物語の世界を遊べるんだ!」とびっくりしたからなんです。
本にも書いていますけど、僕はひとと争うことが大嫌いで、スポーツにもいっさい興味がない。でも『マリオ』や『ドラクエ』は自分との戦いだし、『ポケモン』もひとりで街をうろうろして、面白い物語が読めたり変なモンスターを見つけたりするのが楽しい。要は自分が面白いかどうかで、そういう意味では一貫しているんですよね。だから今はゲームにはあんまり興味がなくなっているんです。僕が面白いと思ったゲームの未来は見尽くしたような気がしていて。
「自己完結じゃないか」と言われたら「何が悪いの?」みたいな。
友達のいない人にも優しいのがテレビゲームなんですよ。僕は友達は多いタイプなんですけど、ひとり遊びもすごく好き。ひとと競うのが好きじゃないから会社勤めもできないんですよ。ライバルを蹴落として出世したいとか、そういう欲がまったくないし。現場で黙々とドット絵を描いたり、黙々とシナリオを書いたりだけしていられれば幸せなんです。
でも徐々に力がついて、年齢も上がってくると、会社としては「チームリーダーにしなきゃ」となるじゃないですか。そうすると部下ができて、人事評価みたいなことをしなきゃいけなくなる。部下の悪いところを見つけて上司に報告するのなんてイヤだし、「あー、俺は会社に向いてないわ」っていつも思っていました。
だんだんわかってきました。他人とご自分との間に優劣や上下の関係を作りたくないんですね。
逆に言えば無責任なんですよ。責任を負うのは家族だけで十分です(笑)。
そう考えると、娘さんも大きくなってこれからが本番ですね。
娘は僕より貯金していますからね(笑)。「お父さん、貯金○○万超えたよ」「か、貸して」みたいな会話をしています(笑)。

撮影/阪本勇(@sakurasou103)

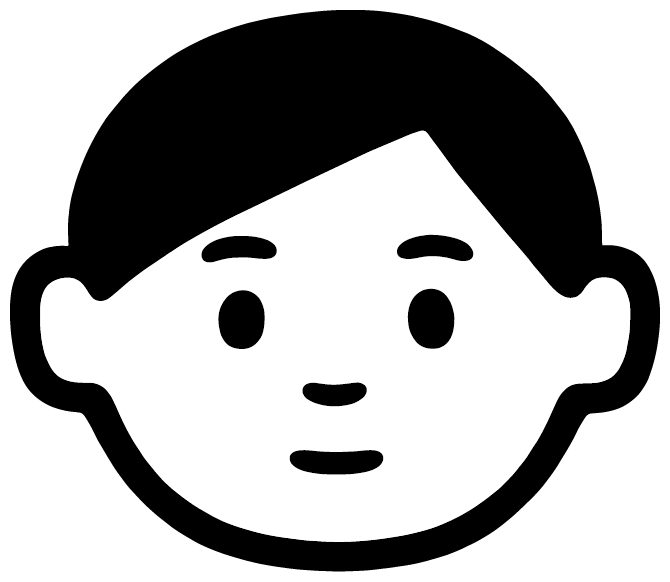 FREENANCE MAG
FREENANCE MAG 


